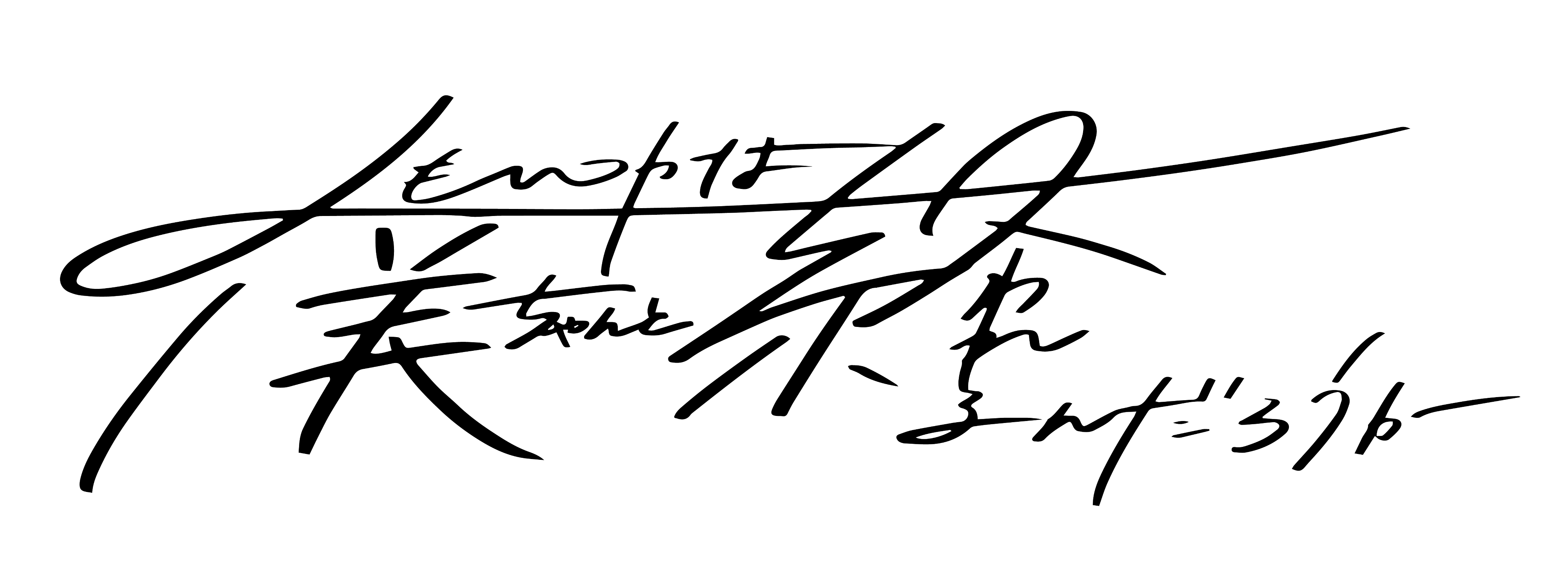最近気づいてしまったのだけれど、わたしはどうやら誰のことも愛せないようだ。なぜかはわからないけれど、確信がある。
黒板に綴られていく数式をノートに書き写す。この先生なら、わたしの悩みを聞いてくれるかもしれない。
やがてチャイムが鳴った。昼休みだ。わたしは教室を出ていく先生を追いかける。
「先生、ちょっとご相談があるんですが」
「いいよ。職員室で聞こうか。でも、お昼ご飯はいいの?」
「はい、食欲がなくて……」
「うーん、なにも食べないのはよくないと思うけど……。まあいいか」
話しながら歩くうちに、職員室についた。先生は自分の席に座って、隣の椅子をわたしに勧めた。
「座っていいんですか?」
「いいよ。今日、カキノキ先生はお休みだから」
わたしは勧められた椅子に座って、先生と向きあう。
「で、相談って?」
「えっと……、わたし、誰のことも愛せないみたいなんです」
「どうしてそんなことがわかるの? まだ愛する人に出逢えてないだけじゃない?」
「いや、どうしてかはわからないけれど、はっきりわかるんです」
「うーん、まあ確かに、そういう人も世の中にはいるからね……。べつに、いいんじゃない?」
先生は机の上の書類を動かしながら、そう言った。
「でも、なんだか寂しい気もするんです。誰も愛せないって……」
「じゃあさ、誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ」
「誰でもない人……、って、誰ですか?」
「だから、誰でもない人」
「誰でもない人なんて、いないでしょう?」
先生はわたしを見て、にっこりと笑った。
「さあ、どうかな? 世界は広いからね。どこかにいるかもしれないよ?」
「はあ……」
わたしは午後の授業を受けおえて、家に帰って自室に引っこんだ。やけに眠くて、制服のままベッドに寝転がる。
誰でもない人、誰でもない人……。
そのうちわたしの意識は闇の中へと沈んでいった。
わたしは海を眺めていた。波は静かだ。
「やあ」
振りかえると、黒く長い髪を垂らした中性的な顔立ちの人が立っていた。
「あなたは誰?」
わたしは思わずそう訊ねる。あたりには誰もいない。
「誰でもないよ。ボクは、誰でもないんだ」
「誰でもない人なんて、いるのかな」
「いるよ。現にボクは、誰でもないんだから」
背後から、静かな波の音が聞こえる。そういえば、一体ここはどこなのだろう。
「でも、あなたはあなたでしょう?」
彼(彼女かもしれない)は、右手で長髪をもてあそびながら、口を開いた。
「実はね、こっそり教えてあげるけど、ここはキミの夢の中なんだよ」
「え、そうなの?」
「そう。キミの夢の中のボクは、現実世界にはいない。だから、誰でもないんだ」
わたしは先生の言葉を思いだした。誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ、という。
「じゃあ、愛していい?」
「ボクを?」
「うん。誰でもないんでしょう?」
「愛してくれるのはうれしいけど……、ボクは誰でもないよ?」
彼(彼女かもしれないけれど、彼ということにしておく)は、今度は左手で髪をいじくる。
「だからだよ。わたし、誰のことも愛せないの。だから、誰でもないあなたのことなら、愛せる」
「うーん、そういうもんかなあ?」
彼は少し困ったように首を傾げる。
「きっとそうなの。ねえ、名前はなんていうの?」
「ボクは誰でもないんだから、名前だってないよ」
彼はそう言って、儚げに笑った。
「じゃあ、わたしがつけてあげる。そうだなあ……」
わたしは空を見上げた。夕暮れなのか、空は真っ赤に染まっている。
「えっと、あなたの名前はクレナイ。どうかな?」
「クレナイ……、うん、いいね。じゃあ、クレナイで。よろしくね、ミウ」
クレナイはにっこり笑って、右手をわたしのほうへ差しだす。わたしは右手をクレナイの手に重ねながら、訊ねた。
「どうしてわたしの名前を知ってるの?」
「そりゃあ、ボクはキミの夢の中にいるんだもの」
「そういうもん?」
「そういうもんだよ。さあ、一緒に海でも眺めよう」
クレナイが砂の上に座ったので、わたしもその隣に腰をおろした。
「どうして誰のことも愛せないの? 人間は醜い生き物だから?」
「そんなこと思ってないよ? 優しい人だって、たくさんいるし……」
「じゃあ、どうして?」
海は静かに波打っている。そしてどこまでも、広がっている。
「わからない。どうしてかはわからないけど、でもわたしが誰のことも愛せないっていうのは、なぜかはっきりわかるの」
「ふーん……」
クレナイはどこか納得いかないように頷いた。
「でも、まだ出逢ってないだけかもよ。愛せる人に」
「いや……、きっと、出逢えない」
わたしはきっぱりと言い放つ。
「まあ、いいけどさ。寂しくないの?」
「寂しいとは、ちょっと思う……。でも今は、クレナイがいるから」
「そっか」
静かな波の音の他に、なにも音はなかった。ふと空を見上げると、真っ青に晴れ渡っていた。わたしは携帯電話で時間を確かめようと、ポケットを探る。けれど、ポケットにはなにも入っていなかった。
「ねえ、いま何時かな? さっきまで空が赤かったから夕暮れなのかと思ってたけど、今は昼間みたいに青いよ」
「夢なんだから、時間なんてないよ。空だって気まぐれに色を変えるさ。ほら、もう一回、見上げてみて」
言われるままに空を見上げると、今度は紫色になっていた。
「へえ……」
左手に何かがあたったので見下ろすと、クレナイの右手だった。
「手でも繋がない? ボクたち、愛しあってるんでしょ?」
「クレナイもわたしのこと愛してくれるの?」
「うん」
わたしはクレナイと手を繋いだ。あたたかい。
「でもまあ、『愛します』って言って愛するものでも、ない気がするけどね……。まあ、夢だからいっか」
わたしは目を閉じて、左手に意識を集中させた。確かに、クレナイの言う通りなのかもしれない。いや、よくわからない。
「そもそもミウは、愛がなんなのか、知ってるの?」
「さあ……、知らない」
わたしは目を閉じたまま応える。
「それじゃあ、人を愛せないかどうか、わからないんじゃ?」
「愛がなんなのかは知らないけど、わたしは誰のことも愛せない、っていうのは、わかるの。うまく説明できないけど……」
そう応えて、わたしは目を開いた。
「そっか……。まあ、そこまで言うなら、そうなのかもね」
クレナイは繋いでいた手を離して、わたしを抱きしめた。
「ボクは……、ミウはいつか誰かを愛するような、そんな気がするよ」
「どうして?」
わたしはクレナイの肩に頭をのせて、また目を閉じた。なんだか、心地よい。
「なんとなく、ね」
波の音がさっきより大きい。目を開くと、目の前に海があった。びっくりしてクレナイから体を離し、辺りを見回す。クレナイとわたしは砂の上にいるけれど、左右前後、周りは全て海になっていた。
「どうしたの、ミウ?」
「どうしたの、って……。周りが全部、海になってるよ……!」
「大丈夫だよ、そんなに慌てないで。ただ……、そろそろお別れみたいだね」
「え、お別れって、どういうこと?」
「うーん……」
クレナイは困ったように唸る。
「キミはもうすぐ、目覚めちゃうから」
「そうなの? ねえ、また次の夢で会える?」
わたしはクレナイに抱きつきながらそう訊ねた。
「会えないと思うよ。ボクは、誰でもないから」
「意味わかんないよ。寂しいよ、またわたしの夢に出てきてよ」
「大丈夫、キミは目が覚めたらボクのことなんて忘れちゃうから」
波がどんどん激しくなり、クレナイを、わたしを、濡らす。
「そんなこと言わないでよ。絶対に忘れない」
「うーん、どうだろうね……」
寂しそうなクレナイの微笑みは、波に呑まれて見えなくなってしまった。
わたしはベッドの上に転がっていた。眠ってしまっていたようだ。なんだか違和感を覚えて、自分の頬に触れた。少し、濡れている。夢を見ながら、泣いていたのだろうか。
どんな夢を見ていたのか、思い出せない。
ただ、なにか大切な夢だった気がする。
またすぐに眠れば、夢の続きを見られるかもしれない。そう思って目を閉じた。けれど、眠ろう眠ろうと思うほどに、意識は冴える。
わたしは諦めて、ベッドから起き上がった。
ふと、先生に言われたことを思いだす。
——じゃあさ、誰のことも愛せないなら、誰でもない人を愛したらいいよ。
誰でもない人、なんて、どこにいるのだろう。いつか、誰でもない人に、出逢えるのだろうか。
21.12.06