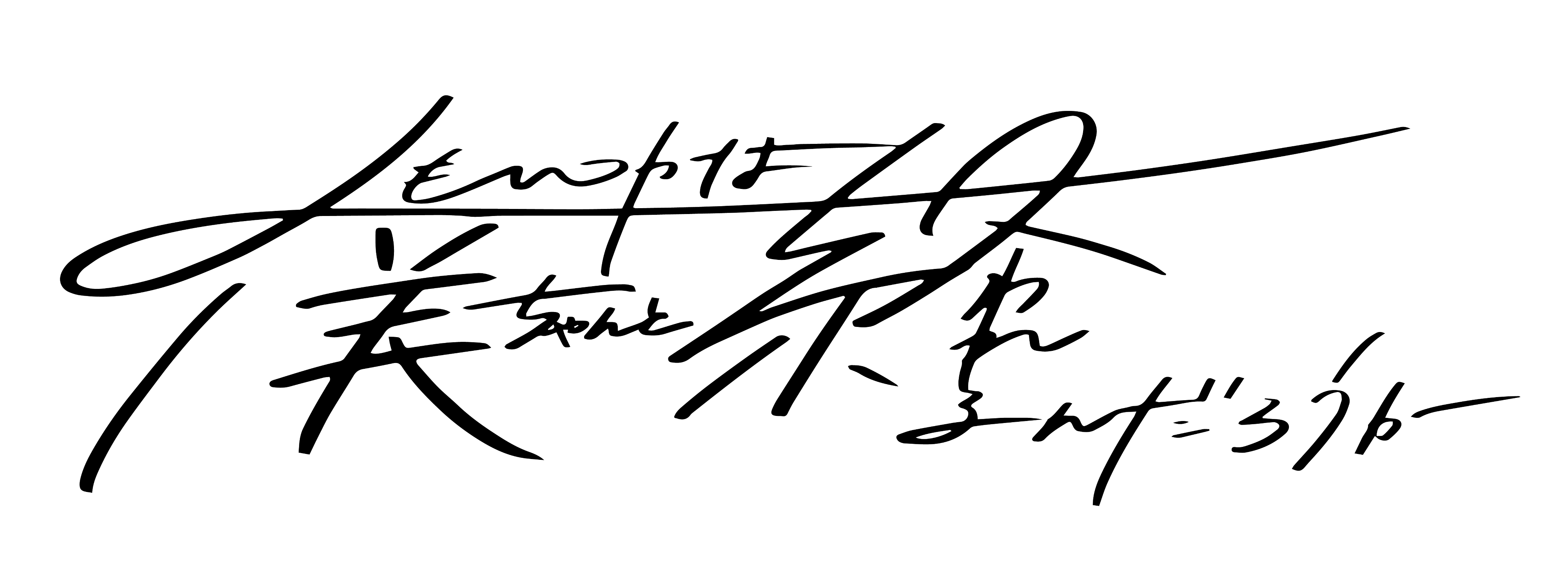人気のない黒い森の中を歩いていた。周りの木には葉が生い茂っているのに、その中に一本だけ、乾涸びきった枯れ木があった。
引き寄せられるように、僕はその枯れ木へと近付いた。近付けば近付くほどに、その枯れ木の枝の至る所に、首を吊るための縄がひっかかっているのが分かった。
とは言ってもその縄たちはどれもこれも、首を吊る側の輪っかが枝に通されていてぶら下がっていた。
僕はもっとその枯れ木に近付いて、そしてそこに妙なヒトがいることに気がついた。
黒いスーツを来たそのヒトは大きな切り株に座って足を組み、右手はその足の上で握っている。その右手は黒かった。真っ暗闇のような色だった。
そしてそのヒトは左手を高く翳していた。
いや……、左手ではない。
スーツの袖からは、枯れ木が生えていた。そしてその枯れ木の枝のあちらこちらに、首を吊るための縄の輪っかが、ひっかかっている。
例えば友達が一度試したように、縄を枝にくくりつけて輪っかを垂らすのとは、逆さまの方向に。
スーツを着たそのヒトは、僕を見た。
その顔も真っ暗闇のように黒くて、なんだか僕の存在すべてが吸い込まれてしまいそうだった。けれど、なぜかそのヒトがニヤリと笑んでいるのがわかった。
目も口も見えないのに。
「吊りたいならどうぞ持っていってくださいな」
そのヒトは、見えない口で——あるいはもしかしたら、そもそも存在しない口で——そう言った。ただただその声は、なんだか優しく僕の耳朶を打った。
その言葉に甘えて、僕はひとつの縄に手を伸ばした。けれど、とても届く高さではない。
風に揺られて枯れ木も少し震え、ひとつだけ縄が動いた。そしてするりと地面に落ちた。僕はその縄に駆け寄って、拾い上げる。
「ところで、君はほんとうに吊りたいの?」
左腕から枯れ木を生やしたそのヒトが、優しい口調でそう呟いた。
「僕じゃないんですよ。吊りたがっている友達に、プレゼントしたいんです」
「ああ、それはとても素敵な贈り物だね」
相変わらず顔は見えないのに、そのヒトが優しく微笑んでいるのが、僕には解った。
拾った縄を握りしめて、僕はそのヒトに小さく手を振った。
22.07.17