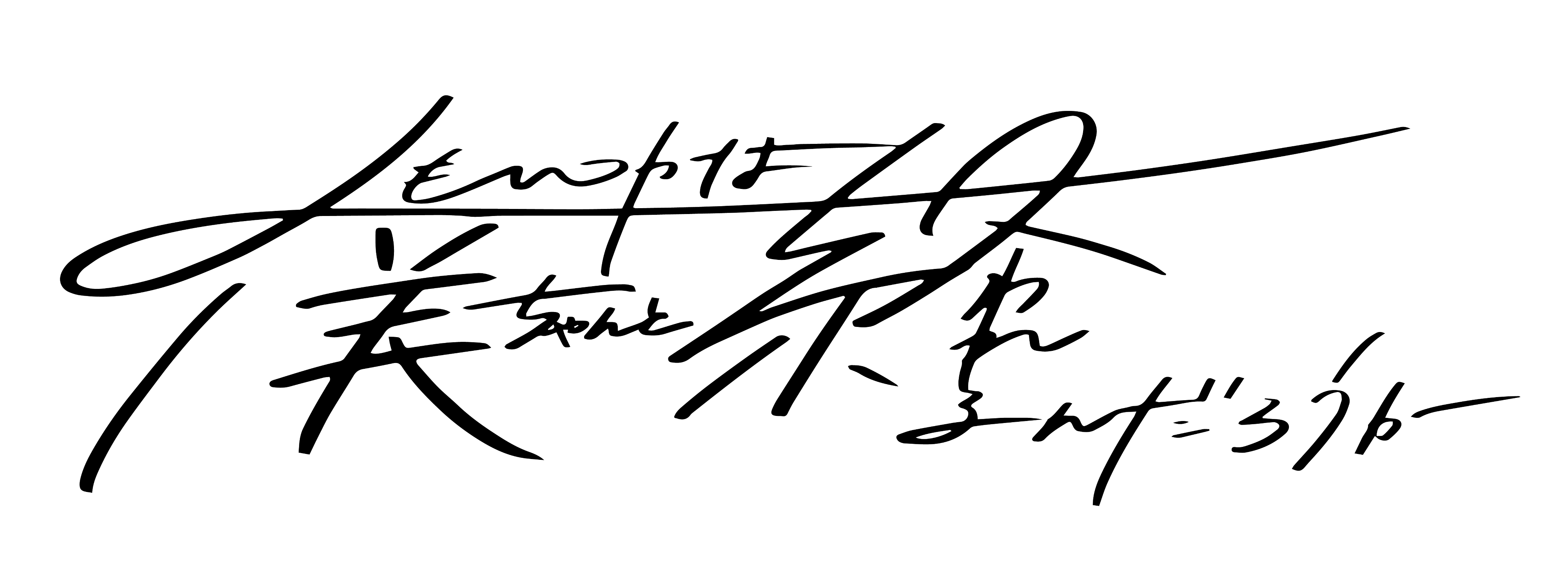1.
「まあ、きっとそのうち忘れちゃえるよ」
うなだれているホツエに、わたしは適切なのかどうかわからないまま、そんな言葉を投げかけた。ホツエはゆるゆると頭を横に振る。それにあわせて、明るい茶色に染められた髪が少し揺れた。その隣ではシズエが頬杖をついてホツエのほうを見ながら、そうそう、と呟く。
学食でホツエとシズエとわたしは毎週そうしているように、三人で食事をとっていた。そして今日は先週に引きつづき、失恋して傷心のただなかにあるホツエを、わたしとシズエは慰めている。果たして慰めになっているのかどうかは、確信が持てないのだけれど。
「忘れちゃえる……、か」
ホツエが小さく呟いて、顔をあげた。そして窓の外へと目をやる。
「ごめん……」
わたしは思わずそう言った。
「どうして謝るの?」
「いや、なんか、気に障ったのかな、て……」
こちらに目を向けて問いかけるホツエに、わたしはそう答える。
「そんなんじゃないよ。でもさ……」
そこまで言って、ホツエは言葉を区切った。
「でも?」
「忘れちゃいたいけど、なんか、忘れちゃうのって、すこし寂しいような気もして」
続きを促すシズエに、ホツエが言葉を続た。
「人は忘れる生き物だよ」
シズエがそう言うとホツエは、そうだね、と言って少し笑った。それから手元のコップを手にとり、水を飲む。わたしもなんとなくそれにつられて、自分のコップを持って口元へと引きあげた。水を少しだけ口に含んで、舌の上で転がしてみる。遠くのテーブルから、知らない学生の大きな笑い声が聞こえた。
シズエは、忘れたのだろうか。高校二年生のときだったか――冬の寒い日だったことだけは覚えている――恋人にフラれちゃったよ、とシズエはあっけらかんと言った。ホツエはびっくりしたように、なんで、どうして、と繰りかえしていた。次第に、シズエを振るなんてありえない、と怒りはじめた。シズエはそんなホツエを笑いながらなだめていた。けれど数日後、ホツエはこっそりとわたしに教えてくれた。シズエ、ほんとうはめちゃくちゃショック受けてるみたいなの、と。夕食に手をつけず、ずっとぼんやりどこか遠くを見てるの……。
わたしがいるときには、ホツエは笑っていた。確かにその笑顔はどこか寂しげに見えた……、ような気もする。
ホツエとシズエは、似ているのに似ていない。わたしはふと、二人の顔をさっと見比べて、やっぱり似ている、と思った。
「どうしたの?」
シズエがわたしに問いかける。
「いや……、ホツエとシズエって、メイクの仕方が全然違うな、って……」
わたしは慌てて適当な――今までにも思ったことはあるけれど、ただそれをとっさに思いだせただけのこと――を、言う。
「双子だからってメイクまで同じにはしないよ」
そう言ってシズエが笑った。
「というか、むしろ顔が同じだからメイク変えてるの」
シズエの言葉を引きつぐようにホツエが言う。
「そうなの?」
「そんなわけないじゃん。双子だって好みまで一緒にはならないってだけ」
思わず問いかけたわたしに、シズエが笑いながら答えた。シズエの短い黒髪に、窓から差しこむ日の光が跳ねる。
「じゃあ、二人ともこの大学に来た理由は?」
わたしがなんとなくそう訊ねると、シズエが少し眉をひそめつつ口を開いた。
「言ったことなかったっけ。お父さんがここ出身でさ。それで学費も安いし、家から通えるしで、ここに入ってほしいって言われて」
「こっちとしてもさ、大学どこにするかとか悩む手間はぶけてラクだったんだよね。大学なんてどうせどこも一緒だろうし」
ホツエがシズエの後を続ける。わたしは、そんなことはないんじゃない、という言葉を口に出さずに飲みこんだ。
「アリカはどうしてここに入ったの?」
シズエに訊かれて、わたしは少し答えに詰まった。ホツエとシズエが行くって言ったから、と素直に答えるのは、なんだか恥ずかしかった。
「いやあ、なんとなく……」
濁したわたしの答えにシズエは、ふうん、と軽く相槌を打った。
「でも小学校から大学までずっと一緒ってさ、すごくない、私たち?」
ホツエが笑いながらそう言った。そうだねえ、とシズエはあまり興味なさそうに頷く。わたしは曖昧に笑みを浮かべておいた。
ほんとうにホツエは、表情がくるっと変わってしまう。さっきまでうなだれていたのが嘘のように、今にもはしゃぎだしそうなくらいだ。
「あ、私そろそろ行かなくちゃ」
シズエがそう言って立ちあがった。
「なんだっけ、化学……」
「工学化学だってば。じゃあね」
問いかけるホツエに答えながら、シズエは皿とコップの乗ったトレイを持って去っていく。
「学部とか学科とかは、どこでもいいって言われたの?」
小さくなっていくシズエの後ろ姿を見ながら、わたしはホツエに訊ねた。シズエは工学部に所属しているけれど、ホツエはわたしと同じように理学部に所属している。
「うん。中学生ぐらいまでは、医学部に行ってくれたらいいなあ、とか言われてたけど、まあ冗談じゃないかな。アリカはどうして理学部に、っていうか、数学科にしたの?」
「数学が好きだからだよ。ホツエこそなんで数学科にしたの?」
「私も一緒だよ。数学が好きだったから……」
わたしの問いにホツエは目を逸らしながら、どこか言葉を濁すように答える。
「好き『だった』って、今は嫌いなの?」
「なんていうか、私が好きなのは数学じゃなくて『アキトが好きな数学』だったんだと、思う。馬鹿だよねえ……」
ホツエは苦笑しながらそう言って、コップを手にとった。
「え、ああ、そうだったんだ……」
ホツエの元恋人の名前に少しうろたえながら、わたしは答える。ホツエはコップに口をつけて水を飲んだ。わたしがかけるべき言葉を必死に探していると、ホツエがコップをテーブルに置いて口を開いた。
「アリカは忘れちゃえたの?」
「え、なにを?」
「好きだった人のこととか」
ホツエの言葉にわたしは、うーん、と唸る。
「恋愛感情で、ってことだよね。わたし、そういう意味で誰かを好きなったことって、ないから……」
「ええ、それほんとう?」
そう言いながらホツエが笑ったので、わたしは頷いた。
ホツエの髪は染められて傷んでいるからなのか、窓から差しこむ日の光が跳ねることはなかった。わたしはコップに口をつけて、残っていた水を一気にあおった。少しぬるくなった水が、喉を通りぬけていく。またどこかの席から大きな笑い声が聞こえてきていることに気づいた。
「たしかに好きな人の話とか、恋人の話とか、聞いたことないけどさ。そうだったんだ」
ホツエがそう言ってから、なるほどねえ、と小さく呟いた。
わたしの頭の中ではホツエの言った、アリカは忘れちゃえたの、という言葉が何度も繰りかえされた。忘れてしまえばもう、忘れたいと思うことさえできなくなる。それは、しあわせなことだろうか。ホツエの言っていた「忘れちゃうのって、すこし寂しいような気もして」という言葉を思いかえすと、なんだか胸が軋むような気がした。けれど、わたしはきっとこれまでにたくさんのことを忘れてきたのだろう。忘れたことすら、忘れて。思いだせないのではなく、わたしの脳からすっかり消えてしまったものたち。それらに思いを馳せてみると、確かになんだか寂しいような気がした。たとえそれが、辛い記憶だったとしても。
2.
「覚えてますか、高校でやったでしょう?」
そう言って三谷先生はチョークを手に取り、黒板へと向きなおった。白い数字とアルファベットと記号がずらずらと、黒板の上に並んでいく。
わたしはボールペンを手にとって、あたりを見回した。最前列には学生が一人だけ座って、じっと前を向いて静止している。二列目には誰もいなくて、三列目には三人の学生が疎らに座っている。一人はせっせと手を動かしてノートになにか書きつけているようだった。もう一人は頬杖をついて窓のほうへと顔を少し傾けている。残りの一人はタブレットを黒板へ向けていた。きっと板書を写真に収めようとしているのだろう。
わたしは後ろから三列目の右端に座っている。まだしばらく板書が続きそうだったので、ノートの隅にボールペンで描くともなく描いていた落書きの続きにとりかかった。
教室の後ろの扉が開く音がした。少しだけ振りかえってみると、身をかがめて扉をくぐるホツエと目が合った。ホツエはにこりと笑って、わたしのすぐ後ろの席に着いた。
「まあ、もう大学生ですから」
三谷先生がチョークを動かしつづけながら、振りかえることもなく突然声をあげた。
「いちいち遅刻をどうのこうの言いたくはありませんがね」
そこまで言って、くるりとこちらのほうへと身を向ける。
「やっぱり白崎さん、あなたでしたか。いくらなんでも遅刻の比率が高すぎますよ」
三谷先生の声は学生をたしなめるというよりは、呆れて独り言を呟いているようだった。
「すみません、気をつけます」
ホツエが少し強張った声を張りあげる。
「そうしてください」
そう答えると三谷先生はチョークを持ちなおして黒板に向きなおり、板書を続けていった。
やがて一限の終わりを知らせるチャイムが鳴ると三谷先生は、それでは、と言ってチョークを置いて教室を出ていった。最前列に座っていた学生がのろのろと立ちあがり、黒板消しを手にとって黒板の上に滑らせはじめる。
他の学生たちは席を立ち、続々と教室を出ていく。
「どうしよう、名前まで覚えられてるとは思わなかったよ」
後ろから声が飛んできたので、振りかえる。
ホツエが困ったような顔をしてわたしを見ていた。
「そもそもなんで名前まで知ってるのかな?」
言われてみれば不思議だった。大学の教員がただの学生、それもまだ個別の研究室に属しているわけでもない学生の名前を知っているのは、なぜだろう。
「訊いてみたらいいじゃん」
わたしは思いつきでホツエにそう言った。
「じゃあ、アリカも着いてきてよ」
「いいけど……」
「やった。それじゃあ六限の法律の講義が終わったら一緒に行こうよ。私、次の時間は倫理の講義取ってるけど、アリカは取ってないよね? 行ってくるね、またあとでね」
ホツエはまくしたてるように言うだけ言うと、荷物を持って教室を出ていった。わたしはノートと筆記具を鞄の中に放りなげて、いつの間にかわたし以外に誰もいなくなっていた教室で席に着いたまま、黒板をしばらく眺めていた。
ホツエとわたしは六限の法律の講義を終えて、三谷先生の研究室の扉の前に立っていた。
ホツエが息を吸って、吐いて、それから扉をノックする。
「どうぞ」
扉の向こうから声がした。ホツエは扉を開けて、研究室の中へと踏みだした。わたしもそれに続く。
「今日はすみませんでした」
「今日『は』ですか」
「えっと……、今までも、あとこれからももしかしたら……」
三谷先生はホツエの言葉を受けて、ふっと息を吐く。
「まあいいんですよ。単位に響かせるつもりもありませんし。まさかわざわざここまで謝りにくるとは思いませんでした」
「えっと……、その、どうして私の名前をご存知なのかと……」
三谷先生は、ああ、と声を出しながら少し間の抜けたような顔をした。
「そうか、そうですね」
そう言って三谷先生は立ちあがり、部屋の隅にあるソファの上に積まれた紙の束を、机の上へと移動させる。
「まあせっかく来たんです、座りませんか」
「あ、ありがとうございます……」
ホツエはおずおずとソファの端のほうに腰かける。わたしもその横に腰をおろした。
「ところで、どうして東雲さんも一緒に来たんですか?」
三谷先生がまた椅子に座りながら、こちらを見て口を開いた。
「まあ、その、先生のところへ行ったらどうか、と言いだしたのがわたしなものでして」
「なるほど。一人で来るのは心細かったと?」
わたしの答えに頷きながら、三谷先生はホツエに目を向ける。
「えっと……、まあ、はい……」
ホツエは恥ずかしそうに俯いた。
「まあ、いいでしょう。二人ともまだ大人と言うには幼い」
はあ、とホツエが声というよりは音と表現したほうがよさそうな返答を発する。三谷先生はそれを聞いているのかいないのか、なにかを迷っているように首を傾けて目を閉じた。
少しの静寂のあとに三谷先生は目を開いて、それから口を開いた。
「僕は一度見たものや聞いたものを決して忘れないんですよ」
三谷先生の言葉にホツエが、はあ、と怪訝そうな表情を浮かべながらも相槌を打つ。
「あなたたちがこの大学を受験したとき、数学の時間の試験監督は誰でしたか?」
「そんなの知りませんよ」
ホツエがにべもなく答えると、三谷先生は苦笑いした。
「もしかして、三谷先生でした?」
「そうですよ。正確に言うと僕一人ではなく、もう一人、唐沢先生もいましたがね」
わたしが問いかけると、三谷先生が答える。
「ともかく、試験中に受験票を机の上に置いていたことは、さすがに覚えているでしょう」
「そういえば、そうですね……」
三谷先生の問いにホツエが頷いた。
「受験票には替え玉受験を防ぐために、顔写真が貼ってあります。そして当然、名前も書いてある。僕はカンニングしている受験生がいないか、何度も教室の中を歩きまわって、受験票の顔写真と受験生の顔とをチェックしていました。唐沢先生はずっと教室の一番前から、全体を見張っていましたがね」
「つまり……、その受験票の内容を全部、覚えているってことですか?」
ホツエのびっくりしたような声に三谷先生が、そういうことです、と返す。
「すごいですね、全部覚えていて、忘れないなんて……」
ホツエがどこか呟くようにそう言った。
「忘れることができない、と言いかえることもできるんですよ? 白崎さんは僕の講義の七回のうち五回は遅刻してきて、一回は欠席でした。出席率は高いほうですが、遅刻率もダントツで高い」
「え、私そんなに遅刻してました?」
「ええ、そんなに遅刻してましたよ。まあ、学生の本分は遅刻せずに講義に出ることではなく、勉強することですからね」
「そ、そうですよね……」
わたしは二人の会話を聞きながら、思わず三谷先生の頭のあたりをじっと眺めてしまう。そこにすべての記憶が詰まっている……。いくら記憶が物理的なスペースを必要しないとはいえ、それはとてもありえないような話に思えてしまった。けれど現に三谷先生はホツエの苗字もわたしの苗字も覚えていた。
「東雲さん、あなたは七回のうち七回とも遅刻せずに出席です。ただ……」
自分の名前が三谷先生の口から出てきて、わたしは思わず身構えた。
「どうも落ちつきがありませんね。しょっちゅう周りを見回しているでしょう。なにか気になることがあるんですか?」
「い、いえ……」
わたしは乾いた声で答えながら、思わず視線を泳がせてしまう。
「まあ、ないならいいんですが」
「あの、先生は私たちのフルネームも、覚えてるんですか?」
ホツエがそう問いかけると、三谷先生は小さな苦笑を顔に浮かべた。
「白崎ホツエさん、それから東雲アリカさん、ですね」
小さく息を呑んで、ホツエはそのまま固まってしまう。
「信用されないのは慣れていますよ」
「い、いえ、あの……」
「いいんですよ。だから、バレないように気をつけているんですがね。うっかりしていました」
三谷先生はそこで言葉を区切って、それからまた口を開く。
「僕はそろそろ夕食をとりに行きたいんですが、いいでしょうかね」
「は、はい……、ありがとうございました」
ホツエは少し慌てるようにそう答えながら、ソファから立ちあがる。つられてわたしも立ちあがった。ホツエは、失礼しました、と言って研究室の扉を開き、廊下へと滑りでる。わたしもそのあとに続いてから、扉を静かに閉めた。
「わたしもちょっと思ってた」
廊下を歩きながらホツエが言う。
「なにを?」
「アリカ、なんかきょろきょろしてるって」
「ああ……」
わたしは歩幅を調整しつつ相槌を打った。
「いや、あのね、ノートに落書きしてるんだけどさ……、中学のときにそれで先生にめちゃくちゃ怒られたことがあってさ……」
「ああ、あったねえ。そんなに怒ることじゃないでしょって思ったの、覚えてるよ」
ホツエはそう言って少し笑った。
「数学は好きだけど、今の講義ってまだ高校でやったこととあんまり変わらないからつまらないしさ」
なぜかわたしはホツエに言い訳をする。ホツエは、うんうん、と頷いた。
「絵を描きたいなら、美術サークルにおいでよ」
ホツエとシズエが美術サークルに入っていることは知っていたし、誘われたのも一度や二度ではなかった。わたしは、うーん、と唸って、それから口を開いた。
「わたしは落書きしかしてないから……」
「私はアリカが高校の美術の授業で描いてた絵、すごい上手だと思ったんだよ。落書きしかしないなんてもったいない」
ホツエは歩きながらもこちらへ顔を向ける。
「とりあえずさ、ちらっと部室だけでも見に来ない?」
「そうだね……、見るだけならまあ……」
今まではそこまで誘ってはこなかったのに急にどうしたのだろう、と思いつつも、おそらく大した意味はないのだろう、と自分で勝手に答えを出して、わたしは頷いた。
「じゃあ来週ね。先輩に見学したい子がいるって伝えとくから、一緒に行こうよ」
3.
わたしは夕飯を食べおえて自室へ戻り、机の前の椅子に座った。抽斗を開けて、その中から日記帳として使っているノートを取りだし、机の上に置いてあるボールペンを手にとる。そして、ノートを開いてボールペンを走らせる。
ホツエが三谷先生の講義に遅刻してきて、三谷先生に小言を言われたこと。ホツエが三谷先生に謝りにいく(というよりは、どうして名前を知っているのかを訊きにいく)のについて行ったこと。そして、三谷先生が一度見たものや聞いたものを決して忘れないということ。ホツエから美術サークルの見学に誘われたこと。
そんなことをつらつらと、日記と言えるのかよくわからない箇条書きで記していく。
一度見たものや聞いたものを決して忘れることがないというのは、いったいどんな感じなのだろう。つらい記憶も決して忘れることができないのだろうか。
「ここが美術サークルで使ってる部屋だよ。みんな部室って呼んでるけどね」
シズエがそう言いながら、窓を少しずつ開ける。小さめの教室の中央には机があり、その周りにいくつか椅子が置かれている。机の上には画材であろうものが雑多に置かれていた。描きかけの絵のようなものもいくつかある。教室の後ろには棚があって、そこにはいくつもの箱が並んでいる。そして窓際には大きなキャンバスが並んでいた。
「ああ、それね、イーゼルにキャンバスを立てかけてあるの。油彩をするための」
わたしがキャンバスに目を向けていると、ホツエがそう教えてくれた。
「イーゼル?」
「うん、ほら、棒みたいなのがあるでしょ。キャンバスを斜めにしてちょうどいい高さに置くために支えてるあの棒、イーゼルって言うんだよ」
「へえ……、たしかに、なんか聞いたことあるような気もする」
わたしは右端にあるキャンバスに描かれた、青いひまわりの絵にふと目を奪われた。今にも崩れてしまいそうな、儚い色。
「晴野先輩来ないねえ」
ホツエはそう呟いて腕時計に目を落としていた。
「あのね、アリカ、申し訳ないんだけど私たち、さっき急用ができちゃってさ」
シズエが言う。
「もう行かなきゃだから、ここで晴野先輩待っててくれる? アリカが来るのは伝えてあるから」
「うん、いいよ。行ってらっしゃい」
「ありがとう、ごめんね! じゃあ行こう、ホツエ」
ホツエとシズエは慌ただしく部屋を出ていき、わたしは一人「部室」に取りのこされた。さっき気になったキャンバスに、そろそろと近づいてみる。
草むらから生える一輪のひまわり。硝子細工のような、透きとおった青い色の、ひまわり。それはキャンバスに触れたら崩れてしまうんじゃないかと思えるほどに、儚げだった。
どうすればこんなに美しい色を描くことができるのだろう。
さっきホツエは、これを油彩だと言っていた。油彩なんて触ったこともない。水彩絵の具は持っているけれど、それもほとんど使ったことはなかった。それこそ学校の美術の授業で何度か使っただけだ。いまさら、わたしのような初心者がこんなところに来てよかったのだろうか、と不安になる。
「どう思う?」
突然背後から聞こえた声に、わたしはびっくりして慌てて振りかえった。そこにはすらりと背の高い人が立っていた。茶色がかった短い髪が、窓から吹きこんだ風に少しだけ揺れる。
「もしかして僕が入ってきたの気づかなかった?」
「あ、はい、すみません……」
わたしはしどろもどろに答える。
「謝らなくていいよ。で、その絵どうかな? 僕が描いたんだけど」
その人は少し恥ずかしそうに、笑いながら言った。
「すごく……、好きです……」
わたしは回らない頭でとっさに答えてしまってから、自分に落胆した。もっと他になにかあるだろう……、と。
「ありがとう、うれしいよ」
けれどその人はほんとうにうれしそうに、そう言った。
「君が東雲アリカさん?」
「そうです」
「来てくれてありがとう。僕は晴野カナメ。この美術サークルの副部長」
「そうなんですね、よろしくお願いします」
「白崎さんたちと一緒に来るのかと思ってたけど」
晴野さんは少し不思議そうにそう言った。
「さっきまでここに二人ともいたんですけど、急用があるからごめん、って言って帰っちゃいました」
「そっか、とりあえず見学って話だから、そうだな……、僕が絵を描くところでも見てもらおうかな。他の部員もいればよかったんだけどねえ」
晴野さんはそう言いながら、部屋の後ろにある棚へと歩いていき、箱を一つ手にとった。そしてその箱の中から、絵の具のチューブが入っているのであろう箱とパレット、筆、そして透明な空き瓶と液体の入った瓶を取りだした。画材を机の上に置き、液体の入った瓶を持ちあげる。
「油彩ってやったことある?」
「いえ、まったく……」
わたしが答えると晴野さんは、そっかそっか、と頷いた。
「ちょっと、オイルを出すから、においがするかも」
そう言って晴野さんは液体の入った瓶と空き瓶の蓋を開けて、瓶から瓶へと少しだけ、うっすら黄色がかった液体を移した。なんだか不思議な香りがする。甘くないのに甘いような、初めて嗅ぐはずなのにどこか懐かしいような。
「これは今、油彩で描いてるんだけど、油彩の絵の具は水じゃなくてオイルを使って薄めるんだ」
説明を聞きながら、わたしはまた晴野さんのキャンバスを眺める。わたしもこのサークルに入って絵の練習をすれば、こんなふうに美しい絵を描けるように、なれるのだろうか。
「描いてるところを人に見てもらうっていうのも、ちょっと恥ずかしいけど……」
そう言って晴野さんは微笑む。そして絵の具のチューブを箱から取りだして、楕円形の木の板の上に青い色と白い色を出した。それから筆をオイルにつけて、ふたつの色をそっとかき混ぜる。青と白は、あっという間に空色に変わった。そして晴野さんは、筆をキャンバスの上に置いた。ぽんぽんと軽く叩くかのように、筆を動かす。ひまわりが少しずつ、透明感を増していく。
「この絵のタイトル、なんだと思う?」
筆を動かしながら、晴野さんが訊ねた。
「タイトルですか……、『硝子のひまわり』とか……?」
「硝子みたいに、見える?」
「はい……、硝子細工みたいだなって、思って……。すみません」
わたしはなんとなく気まずいような気持ちになりながら、そっと謝罪の言葉を付けたす。
「なんで謝るのさ。僕の狙いどおりでうれしいよ」
晴野さんはそう言って、こちらに顔を向けて優しく微笑んだ。そしてその表情に、わたしはほっと胸を撫でおろす。
「それで、タイトルはなんなんですか?」
「『砕けないで』だよ」
わたしが問いかけると、晴野さんは少し恥ずかしそうにそう答えた。
「『砕けないで』ですか……、素敵なタイトルですね」
「ありがとう」
それからしばらく、晴野さんは黙ったまま筆を動かした。ときどき筆をオイルにつけ、新しい空色を木の板の上で作りだし、そしてその色をひまわりに乗せていく。
「東雲さんは水彩派かな?」
ふいに晴野さんが筆を動かしながら声を発した。
「いえ……、水彩も美術の授業で少しやったぐらいで……、わたしはその、落書きばっかりで、なんというか、ちゃんとした絵って授業以外で描いたことなくて……」
わたしは少し恥ずかしさを覚えながら答える。
「そうなんだ。初心者でも大歓迎だよ? せっかく絵を描くのが好きなら、水彩も油彩もやってみるだけやってみたらいいと思うんだ。ここならいくらでも画材があるからさ、ぜひ入りなよ」
「えっと、はい、ありがとうございます……」
わたしが迷いながらも答えると、晴野さんは満足そうに頷きながら、また新しい空色を作った。キャンバスの中のひまわりは、透明感とともに儚さをも増していく。ときどき窓から吹きこむ風に晴野さんの髪が揺れて、わたしはそれに少しだけ見入った。
「こんなもんかなあ」
ふと晴野さんはそう呟いて、筆を机の上に置いてこちらを向く。
「すごいです、さっきもすごく素敵だったけど、もっともっと素敵になってますね……」
わたしはどこか興奮を覚えながら、青いひまわりと晴野さんとに、交互に視線を走らせた。
「ありがとう。で、どうする? 入部してみる? もし飽きちゃったり嫌になっちゃったりしたら、いつでもやめていいからさ」
「はい……、ぜひ入部したいです」
わたしの中にあった迷いはもはや消えていた。
「それはうれしいな。じゃあ、部員がみんな集まることってほとんどないから、今度の月曜日の六限が終わってから顔合わせにしようかな。大丈夫?」
「はい、大丈夫です。よろしくお願いします」
「うん、他の部員には僕から声をかけておくから」
「ありがとうございます」
晴野さんはにっこり笑って、机の上の画材を箱の中へと戻しはじめた。
「じゃあ、今日はお開きにしようか。ほんとうは他にも何人かいるときに見学してもらったほうがよかったとは思うんだけど、ごめんね」
「いえ……、大丈夫です」
わたしがそう言うと、晴野さんはまた微笑んだ。
「それじゃあ、気をつけて帰ってね」
「はい、今日はありがとうございました。これからよろしくお願いします」
「こちらこそ。君と一緒に絵を描けるの、楽しみにしてるよ」
4.
「新しくこのサークルに入ってくれる人がいるから、軽く自己紹介してもらおうかなと思います」
美術サークルの部室の四方に部員たちが散らばっていて、部屋の中央の机の前で晴野さんがそう言った。それから部屋の隅にいたわたしのほうを見て、手招きをする。わたしはそろそろと晴野さんの近くへ歩いていった。
「理学部の一回生、東雲アリカと言います。えっと……、白崎ホツエさんとシズエさんに誘われて、サークルに入ることにしました。なんというかその、ちゃんとした絵、みたいなのは美術の授業でしか描いたことのない初心者ですが、よろしくお願いします」
机の近くにいた人が拍手をした。わたしはなんだか恥ずかしくなって、思わず俯く。晴野さんが口を開いた。
「前にも言ったけど、僕が副部長。部長は四回生の甲斐ケントさんっていう人なんだけど、甲斐さんは基本的に夜しかここには来ないんだ。東雲さんが入部することはもう伝えてあるけど、顔を合わせるのはまだしばらく先になるかも」
わたしは、はい、と頷く。
「そっちにいるのが林ユウ。僕と同じ三回生で、工学部」
晴野さんが指さしたのは、部屋の隅にいる赤い髪を肩まで伸ばした人だった。
「どうも」
林さんは低い声で呟くようにそれだけ言った。目つきが少しきつくて、とっつきにくそうな印象を受ける。
「それからこっちが佐々木カンナ。この人も三回生で……」
「文学部だよ。アリカちゃん、わからないことあったらなんでも訊いてね」
さっき拍手をしてくれた佐々木さんが明るい声でそう言って、わたしににっこりと笑いかける。この人は親しみやすそうだな、と思って少し安心する。
「それから、そこにいるのは一回生の川口ヤエさん」
「法学部です。よろしくお願いします」
窓際にいる川口さんは無表情でそう言った。敬語を使われて、わたしも同じ一回生なのになあ、とぼんやり考えた。とはいえ初対面だしなあ、と思いなおす。
部室にいるのは晴野さん、林さん、佐々木さん、川口さんと、あとはホツエとシズエだけだった。
「そういえば、白崎さんたちとの付きあいは長いの?」
「長いですよ、私たち三人、小学校からずっと一緒なんですから」
晴野さんの問いかけに、わたしよりはやくホツエが答える。そのすぐ隣ではシズエもにこにことしながら頷いていた。
「今日来てない部員はまたおいおい紹介するよ。まあ、もしも会うことがあれば、の話だけどね」
「ありがとうございます。えっと……、すみません、なんか中途半端な時期に入部しちゃって」
わたしは少し気がかりに思っていたことを口にする。
「いやあ、気にしなくていいよ? そういう人も結構いるし」
晴野さんは微笑みながら優しくそう言ってくれた。
「えっと、みなさん、どうぞよろしくお願いします」
「よろしくね!」
佐々木さんが明るい声で言いながらわたしに笑いかけてくれる。それから林さんが、ああ、とどこか気のなさそうな相槌を打つ。川口さんは変わらず無表情でわたしのほうを見ていた。
「それじゃあ、ここで使う道具の説明とか軽くするよ。みんなは絵描くなり帰るなり好きにして。今日は集まってくれてありがとう」
「じゃあ俺は帰るわ」
林さんが低い声でそう言って、すたすたと扉のほうへ歩いていく。
「お疲れ」
晴野さんがその背中に声をかけるが、林さんは返事をすることなく扉を開けて部屋を出ていった。
「私も用事があるので帰ります」
川口さんがそう言って、晴野さんのほうへと軽く頭を下げる。
「うん、お疲れさま」
「お疲れさまです。お先に失礼します」
そう答えると、川口さんもすたすたと部屋を出ていった。部屋には晴野さんと佐々木さん、それからホツエとシズエ、そしてわたしの五人が残った。
「そういえば、このサークルって部員は全部で何人いるんですか?」
ふと気になったことを、晴野さんに訊いてみる。
「うーん、所属してるけどなにもしてない人とかもいるからなあ……、そういうのもあわせたら十五人……、とかかなあ」
「まあでも基本は部長と今日いた林にヤエちゃん、それから残ったここの五人で、あわせて八人が主要メンバーだよね。アリカちゃんも今カウントしたからね、幽霊部員にならないでよー、そしたら私悲しいから」
晴野さんの言葉を引きつぐようにして佐々木さんが言って、笑う。
「プレッシャーかけちゃダメだよ」
晴野さんが苦笑いしながらそう言った。
「あ、そうだ、忘れてた。この部屋は朝の九時から、夜も一応九時まで使えるから。事務に申請出せば真夜中まで使えないこともないけど、まああんまりおすすめはしないかなあ……、結構手続きが面倒だから。まあでも、どうしてもってときは僕か佐々木さんに言ってくれればいいよ」
「え、夜中まで使う人いるんですか……?」
わたしは晴野さんの説明にびっくりして、思わずそう訊ねた。
「まあ、甲斐さんとかはたまにやってるみたい。あとコンテストの締め切り間近になるとユウとかも使ってたりするね」
そう言いながら晴野さんは部屋の後ろのほうへ歩いていって、棚から箱を取りだした。
「この箱の中にいろいろ画材とか入ってて、この箱は今誰も使ってないやつだから、東雲さんが使っていいよ。最初はここにあるの使って、感覚が掴めてきたら自分で好みのものを探して買うのがいいと思う」
言いながら晴野さんは、箱を持って机のほうへと戻ってきた。
「わかりました。ありがとうございます」
晴野さんが箱を開けたので、わたしは少し身を乗りだしてその中を覗いてみた。絵の具のチューブが入っているのであろう箱が二つ、パレット、それから水を入れる黄色い容器、油彩に使うオイルの瓶、他にもいろいろとわたしには用途のわからないものが入っていた。
「絵の具とパレットはわかるよね。こっちが水彩で、こっちは油彩」
そう言いながら晴野さんは絵の具のチューブの入った箱を二つ取りだして机の上に置いた。
「それから、これはまあ水入れるやつ。そうだ、これの名前、知ってる?」
黄色い容器を持ちあげて、晴野さんが訊ねる。
「いや、知らないです……」
「筆洗器って言うんだよ。筆を洗う器だから、筆洗器」
「私もこのサークル入ってから知ったよその名前」
へえ、と相槌を打ったわたしの横で、シズエがそう言った。
「で、これが見学のときにも見せたけど、油彩に使うオイル。ペンチングオイルって言うんだ」
言いながら晴野さんは、黄色がかったオイルの入った瓶を机の上に置く。
「それからこれは水張りに使うテープ」
「水張り……?」
聞きなれない言葉に、わたしは首を傾げた。
「えっとね、紙に普通に水彩絵の具で描くと紙が歪んじゃうから、いったん紙全体を水で濡らして乾かすんだけど、それをするとき木の板に貼りつけてやるんだ。それに使うテープだよ。今度やり方教えるよ」
わたしは晴野さんの説明に、ありがとうございます、と答える。
「とりあえずはこんなところかなあ。まあ、他にわからないものがあったら、そのとき訊いてね」
晴野さんはそう言って、机の上に並べた画材を丁寧に箱の中へ戻していく。
「晴野じゃなくてこの佐々木カンナ様に訊いてもいいのよ!」
佐々木さんがおどけるようにそう言って、笑った。
5.
抽斗の中から日記帳がわりのノートを取りだして開き、ボールペンを手にとる。なんとなく今日は丁寧に書きたいと思って、箇条書きではなくて文章で、今日あった出来事を書きつけていった。書きながら、今日初めて会った佐々木さん、林さん、そして川口さんの顔を順番に思いかえす。三人はどんな絵を描くのだろう。そしてわたしはこれから、どんな絵を描くのだろう。
ノートを閉じて抽斗の中へとしまい、机の上に置きっぱなしの小さなスケッチブックを手にとった。ぱらぱらと、これまでに描いた落書きを見返す。こんな落書きしかしたことのないわたしが美術サークルなどに入ってよかったのだろうか、とまた少し不安を覚える。けれど晴野さんは、初心者でも大歓迎だよ、と言ってくれた。なにより、わたしも晴野さんの描いていた「砕けないで」——あの、触れたら壊れてしまいそうな、儚い青い色のひまわり——のような、なにか美しいものを、わたしも描いてみたいと思った。
三谷先生が黒板に数式を連ねていくのをぼんやりと眺めながら、なにを描いてみようか、と考える。今日はこの講義が終われば、六限の法律の講義までは他になにもない。今までは学内の図書館へ行って落書きをしたり、たまに本を読んだりして過ごしていたけれど、これからは美術サークルに参加する時間にあてるのがいいかもしれない。
三谷先生の講義が終わるまでの時間はとてもとても長く感じられた。やがてチャイムが鳴り、三谷先生はいつものように、それでは、と言って教室を出ていった。そして最前列に座っていた学生が立ちあがって黒板に書かれた数式を消しはじめる。わたしはテキストとノートとペンケースを鞄にしまった。
「ちょっとずつ難しくなってきたね」
後ろから飛んできた声に振りかえると、ホツエが少し眉をひそめていた。
「そう……、だね」
わたしは、そうかなあ、と言いかけたのを慌てて言いかえた。
「はあ……、倫理行ってくるね」
ホツエは溜息をついて立ちあがった。
「わたしは講義ないから、部室行ってみる」
わたしがそう言うと、ホツエはにっこりと、ナイスアイディア、と笑った。
ホツエとわたしは一緒に教室を出て、そこで左と右へわかれた。わたしは部室へ向かいながら、なにを描こうか、とまた考える。
なにも思いつかないまま部室にたどりついてしまう。しかたなく扉を開くと、部屋の中には晴野さんがいた。
「こんにちは」
わたしがそう声をかけながら部屋の後ろにある棚へと近づいていくと晴野さんは、やあ、と少し間延びした声で答える。わたしは棚から箱を取って、部屋の中央の机まで持ってきて、箱を開けた。
「そうだ、水張りのやり方、教えとこうか?」
「お願いします」
晴野さんは部屋の後ろの棚へ近寄り、端のほうにある厚い木の板を手にとる。そして机へと戻ってきて、机の上に置かれていた薄くて青い板のようなものに手をかけて、開いた。青いと思っていたのはどうやら表紙のようで、それを開いた中には白い画用紙らしきものが見える。
「もしかしてこういうのも初めて見るかな? これ、水彩用の紙を、四辺とも糊付けしてあるんだ」
わたしは晴野さんの説明を聞きながら、それをまじまじと見つめた。
「つまり……、何枚もの紙の塊、ってことですか?」
そう訊ねると晴野さんは、そうそう、と頷く。
「ここ、ほら、ここだけ少し糊付けされてない部分があって、ここにカッターナイフとか入れて、一枚ずつ剥がせるんだよ」
そう言って晴野さんは紙の塊の間に指を少し差しいれるようにして、隙間を作ってみせた。
「こうやって糊付けしてあるタイプは水張りしなくてもそんなに波うたないんだけどね。普通は糊付けされた状態のまま絵を描いて、描きおわってしっかり乾いてから、その絵を切りはなすんだ」
わたしは、そうなんですか、と相槌を打つ。晴野さんは机の上にあったカッターナイフを手にとって、優しい手つきで紙の塊から一枚を少しずつ剥がしてゆく。
「でも僕はやっぱり、水張りしてから描きたいんだよね」
晴野さんは剥がした一枚の紙を、先ほど持ってきた厚い木の板の上の真ん中に置いた。それから机の上に置かれていた筆洗器を取りあげる。
「ちょっと、水を汲んでくるね」
そう言って晴野さんは、筆洗器を手に部屋を出ていった。わたしはそっと窓際へ目を走らせ、右端にある青いひまわりの絵を眺める。
前に見たときよりもさらに儚くなっているような気がした。
それから、他のキャンバスにも目を向けてみる。青いひまわりの左隣のキャンバスには風景画のようなものが描かれていて、さらにその左のキャンバスには抽象画のようなものが描かれている。わたしはまた晴野さんの描いていた「砕けないで」に目をやった。
壊したい……。
わたしはなぜだか、そんなことを思った。あの硝子細工のようなひまわりにこの手で触れて、ばらばらにしてしまいたい。それから、そんな思いを抱いた自分自身に対して、戸惑いを覚える。
扉が開いて、晴野さんが部屋に入ってくる。
「お待たせ」
わたしは、はい、と頷いた。晴野さんはわたしの近くへ来て、水の入った筆洗器を机の上に置いた。そして机の中央にある何本もの筆の入った瓶から、毛幅の広い筆を取って、その毛先を水につけた。
「あ、テープのこと忘れてた……。東雲さん、ちょっとこの筆持ってて」
わたしは手を伸ばして晴野さんの手から筆を受けとった。指先が少しだけ晴野さんの手に触れて、なぜかわたしは少しどぎまぎしてしまう。晴野さんは部屋の後ろへ歩いていって箱を一つ開け、その中から白いテープを取りだした。そしてこちらへ戻ってきて、テープを少し伸ばして木の板の上で紙に沿わせ、紙の幅より少し長めに切った。
「これ、水張りに使うテープだよ。なんて言うのかなあ、切手みたいに、水に濡れると貼りつくようになるんだ。これを四つの辺に合わせて四本ね」
そう言いながら晴野さんは同じ作業をあと三回、繰りかえした。切られたテープは机の上で、今まで巻かれていたせいだろう、反りかえっている。
「じゃあ、その筆ちょうだい」
わたしはさっき晴野さんから受けとった筆を手渡す。晴野さんはその筆を、板に乗せた紙の上に滑らせた。何度か筆を水につけて、紙全体を濡らしていく。紙全体に水が行きわたると、机の端にある布で筆先を拭いて、机の中央にある瓶へと戻した。そして今度はそこから、細めの筆を手にとる。
「紙を濡らしたら、今度は水張りのテープの糊になってるほうを濡らして、それで紙の端を板に貼りつけるんだ」
そう言いながら筆を水につけ、一枚のテープの片面を濡らして紙の一辺に沿わせ、左から右へと指でなぞった。
「こんな感じ。これを四辺ともね」
晴野さんは同じ作業をもう三回、繰りかえした。
「はい、あとはこれを乾かして絵を描くんだ」
「へえ……。あれ、絵を描きおわったらどうするんですか? 板ごと作品、ってことになるんですか?」
わたしが問いかけると晴野さんは、あはは、と優しく笑った。
「そうじゃないよ。テープの少し内側に沿ってカッターナイフで切りとって、で、板はまた次の水張りに使うんだ」
「ああ、なるほど……」
晴野さんの答えに、わたしは少し恥ずかしさを覚えつつ頷いた。
「それでまあ、乾くのには時間がかかるからさ、一個もう水張りして乾かしたのを用意してあるんだ。東雲さんが来たとき用にと思ってね」
「え、ありがとうございます……」
「でもちょうどよかったよ、今日来てくれて。僕もたまたまこの時間は講義がないからさ」
そう言いながら晴野さんは部屋の後ろの棚へと歩いていき、木の板を手に戻ってきた。確かにその板には、紙が四辺をテープで貼られていた。
「これに水彩で好きな絵を描いてみて」
はい、と答えながら部屋の後ろへと歩いていって、棚から箱を一つ手にとる。机まで戻ってきて、箱の中から水彩絵の具のチューブの入った箱とパレットを取りだして机の上に並べた。水を汲んでこようと思って筆洗器に手をかけると、晴野さんが口を開いた。
「ああ、そっち使っていいよ」
晴野さんは、先ほど水張りをするために使った筆洗器を指さす。
「ありがとうございます」
わたしは瓶から筆を一本取って、椅子に座った。絵の具の箱を開けると、青いラベルがぱっと目についた。
その、青い絵の具のチューブに手をのばす。自分の指が少し震えていることに気づいて、いったいどうしてだろう、と考える。
「久しぶりに絵の具を使うので……、なんか、緊張します……」
なにを訊かれたわけでもないのに、言い訳をするよにわたしは口を開いた。晴野さんは、気にしなくていいのに、とどこかおもしろそうに言った。わたしはパレットの上に青い絵の具を少し出して、筆に水を含ませてそれを薄める。
なにを描けばいいんだろう。
やっぱりなにも思いつかない。水張りされた紙の上に、青い絵の具——いや、うっすら青く色づいた水——を広げる。ね、波打たないでしょう、と言われて、そうですね、と答えたものの、わたしの頭の中は目の前に広がる薄い青とはうってかわって真っ白だった。
6.
「駅の近くにある美術館、知ってる?」
「まあ、はい……。行ったことはないんですけど……」
晴野さんに問われてわたしは答える。
「冬に、そこでコンテストがあるんだ。いろんな大学のサークルの人とか、アマチュアの絵描きさんとかが出展するんだよ。東雲さんも出してみない?」
「そうですね……、頑張ってみたいです」
うんうん、と晴野さんはにっこり笑う。
「そんなに難しく考えることはないからね。水彩でも油彩でもいいし、色鉛筆とかクレヨンとかだっていいんだよ。要するになんでもあり」
「へえ、そうなんですね」
「うちのサークルメンバーは、だいたいみんな毎年このコンテストに絵を出すんだ」
わたしはまた、そうなんですね、と繰りかえす。
「テーマとかもないから、自由に描けるよ。それで、佳作以上に選ばれたら、二ヶ月くらい美術館に展示してもらえるんだ」
晴野さんが言いおわるとほぼ同時に扉が開いて、佐々木さんが部屋に入ってきた。そして、やっほー、と明るく言う。
「佐々木さんも美術館のコンテスト、出すよね?」
晴野さんが問いかけると、佐々木さんは頷く。
「出すよ、まだ描きはじめてないけど! アリカちゃんは?」
「挑戦してみようかなって思ってます」
そっかそっか、と頷きながら佐々木さんは部屋の後ろにある棚へ近づく。そしてはたと立ちどまり、こちらをむいて口を開いた。
「そういえばアリカちゃん、油彩はまだ?」
「まだやったことないですね」
「じゃあ私が教えてあげる!」
佐々木さんはそう言って、箱を一つ手にとって机の近くへ来る。
「あ、ありがとうございます……。でも、難しいんじゃないですか……?」
わたしはおずおずと不安を口にした。
「水彩とそんなに変わらないよ?」
カナメさんが机の上から白い板のようなものを一つ手に取り、椅子を引いてわたしに手招きをした。わたしはそろそろと椅子に腰かける。
「油彩は紙じゃなくてキャンバスとか、あとは木の板とかに描くんだ」
そう言いながら晴野さんがわたしの左隣の椅子に座って、手に持っている白い板のようなものを少し持ちあげてみせる。佐々木さんがわたしの右隣の椅子に腰をおろした。
「キャンバスって、あれですよね。イーゼルに立てかけてある……。イーゼルっていう名前は、まあ、つい最近知ったんですけど」
わたしはそう言いながら、窓際に並ぶキャンバスを指さした。
「もちろんあれもキャンバスだけど、キャンバスもいろいろサイズがあるんだ」
晴野さんがそう言って、机の上、わたしのすぐ前に白い板のようなものをそっと置いた。
「それも小さいけどキャンバスなんだよ」
佐々木さんがそう言いながら、画材を机の上に並べる。
「いきなり大きいキャンバスだと緊張するでしょ? というわけで、これが東雲さんの初めてのキャンバスだね」
晴野さんはそう言って、一度は置いたその白い板のようなものをまた手にとり、わたしのほうへと差しだした。わたしはそれを受けとって、じっと見つめてみる。表面は布のようにざらついていて、裏返してみると釘のようなものがいくつか並んでいた。木の板に布を打ちつけてあるようだ。
「ありがとうございます。キャンバスって、必ずイーゼルとセットなのかと思ってました」
わたしの言葉に晴野さんが笑う。
「僕も昔はそう思ってたよ。あ、小さいキャンバス用の小さいイーゼルもあるけどね。卓上で使うやつ」
「へえ……」
「でもあれは飾り用って感じだよね。これくらいのサイズなら机の上に置いたほうが描きやすいよ」
頷くわたしに、佐々木さんが言った。
「これが油彩の絵の具。まあ、べつにぱっと見は水彩と同じでしょ?」
そう言って佐々木さんが開けた箱の中には、絵の具のチューブが並んでいた。確かにそれは、水彩絵の具のチューブと特に変わらないように見えた。
「でもね、油彩はほんとうに落ちないから、服につかないように気をつけてね」
佐々木さんは言葉を続けながら、黄色がかった液体の入った瓶を掲げる。
「これがペンチングオイル。油彩の絵の具は水じゃなくてオイルで薄めるんだよ」
そう言って佐々木さんは、空き瓶の中へオイルを少し移した。
「で、これが油彩用のパレット」
晴野さんが楕円のような形の木の板を持ちあげる。
「これ、パレットだったんですね」
「うん、これはちょっと水彩とは違うよね。この穴に親指を通して持つんだよ」
そう言って晴野さんはパレットの端に空いた穴に左手の親指を通して、パレットを持ってみせた。それから一度パレットを机に置く。
「この端っこのほうに、何色か出しておくんだ」
そう言って晴野さんは絵の具のチューブを順番に手にとって、いろいろな色を少しずつパレットの端のほうに出していく。
「で、真ん中のほうの空いたスペースで色を混ぜるの」
佐々木さんが晴野さんの言葉に続けるようにして、言った。晴野さんは机の中央にある瓶から筆を一本取った。
「とりあえずまあ、難しく考えずに、適当に好きな色をすくってキャンバスに乗せてみてよ」
わたしは筆とパレットを受けとり、小さなキャンバスと向きあう。パレットの上の青い色の絵の具が、わたしの目を惹く。筆先で青い絵の具をすくいとり、おそるおそるキャンバスの中央に触れさせて、滑らせてみた。少しがさっとした感触が手に伝わる。
「青が好きなの?」
晴野さんがどこか楽しげにそう訊ねる。わたしの脳裏には、ぱっと青いひまわりの絵がよみがえった。なぜかわたしはそのことを、晴野さんに知られたくない、と思った。
「そうですね、まあ……」
言葉を濁して、わたしはパレットの上で青い絵の具と黒い絵の具を混ぜてみた。そしてその色を、キャンバスに乗せてみる。
「キャンバスはいっぱいあるから、遠慮せずにどんどん使っていいよ。なにを描くわけでもなく色を乗せるだけでも、けっこう楽しいでしょ?」
晴野さんの言葉にわたしは、はい、と頷いた。
「なんか、感触が不思議な感じでおもしろいです」
「私も初めて油彩やったときは、がさがさするのが楽しくてキャンバス一面塗り潰したことあるよ」
佐々木さんがそう言って笑う。扉が開いたのでそちらに目をやると、林さんが入ってくるところだった。
「こんにちは」
そう声をかけると林さんは、どうも、と低く呟いて、教室の後ろにある棚のほうへと歩く。
「ユウもコンテスト出す?」
「まあ、そのつもり」
晴野さんの問いに、林さんはそっけなく答える。棚から箱を一つ手にとってわたしたちの近くにやって来て、机の上に画材を並べていく。
「なに描いてんの」
「えっと、なにっていうわけでもなく……」
大して興味もなさそうに訊く林さんに、わたしはなんとなく恥ずかしさを覚えながら答えた。
「油彩のやり方教えてあげてたの」
「ああ、そう」
佐々木さんの言葉に、林さんはやはり興味なさそうに頷く。そして油彩用のパレット ̶ ̶その上にはいろんな色の絵の具がこびりついていた ̶̶の上に絵の具を出していく。林さんはそれを左手に持ち、右手に筆を取って、窓際のキャンバスの前に立った。そのキャンバスには、抽象画のようなものが描かれている。
「それって、なんの絵なんですか?」
「さあ?」
わたしが訊ねると、林さんこちらに背を向けたまま肩をすくめてみせた。
「俺にもわかんねえよ。適当に色乗せてるだけ」
林さんはそう言って、キャンバスに筆を走らせはじめた。
7.
晴野さんはキャンバスに向かって腕を組んでいた。キャンバスの真ん中には、「大なり」の記号を横に長く伸ばしたような形が、大きく黒い色で描かれている。そしてその周りを囲むように、四方八方へといろいろな向きに色とりどりの線がいくつも引かれていた。
「なにを描いてるんですか?」
「『デクレッシェンド』ってタイトル。デクレッシェンドの記号と五線譜のつもりで描いてみたんだけどね」
わたしが問いかけると、晴野さんはこちらを向いて微笑みながら答えてくれた。
「デクレッシェンド?」
聞きなれない言葉にわたしは訊ねかえした。
「音楽記号の一つなんだ。だんだん弱く、って意味。楽譜にこの記号があるところでは、音をだんだん弱くしていくんだ」
「へえ……。もしかして晴野さんって、音楽もされてるんですか?」
「うーん、ちょっとだけ……。小さい頃にピアノ習わされてた。今はたまにギター弾いてるよ」
「えっ、今度聴かせてくださいよ」
わたしがそう言うと、晴野さんは照れるように笑った。
「そうだねえ、君になら少しくらい、いいかな」
なんだか胸が躍る。そしてそのことが、少し恥ずかしく思えた。
扉が開いたので目をやると、林さんが入ってくるところだった。林さんはこちらへ歩いてきて、晴野さんのキャンバスを一瞥して口を開く。
「なに、デクレッシェンド?」
「そうそう」
「え、林さんも音楽されてるんですか?」
わたしは思わずそう訊いた。
「いや、してねえよ。中学だか高校だかの音楽の授業で習ったろ」
「え……、そうでしたっけ。全然覚えてないです……」
林さんはすたすたと部屋の後ろにある棚まで歩いていって、箱を手にとった。
「おもしろい絵だな」
ほんとうにおもしろいと思っているのかよくわからない声で、林さんはそう言った。わたしは林さんから目を離して、また晴野さんの「デクレッシェンド」を眺める。だんだん弱く……。
「そうだ、東雲さんって誕生日いつ?」
「七月一日ですよ」
腕組みをほどいて訊く晴野さんに、わたしは答えた。
「そっか、もうすぐだね」
「晴野さんはいつですか?」
わたしがそう訊ねると、晴野さんはどこか意味ありげに微笑む。
「なに笑ってるんですか」
「一月七日。君のをひっくり返した日だね」
「え、ほんとうですか!」
わたしはまた、自分の胸が躍るのを感じた。そしてすぐに、ひょっとして晴野さんは冗談を言っているだけなんじゃないか、という気がした。
「すげえ偶然」
林さんがやっぱり興味なさそうに、小さく呟く。
「いただきます」
両手をあわせて申し訳程度に呟き、箸を手にとる。焼かれた鮭の切り身を崩して、口に運んだ。
「どうも」
声をかけられてそちらに目を向けると、林さんがいた。
「こんにちは」
「うん」
わたしが挨拶をすると、林さんは短く頷いて、手に持っていたトレイをテーブルの上に置き、わたしの隣の席の椅子を引いて座った。
「コンテストに出す絵、どう?」
「少しずつ描けてますよ。自信はないですけど……」
「そう」
返事はそっけなかったが、林さんがわたしに声をかけてくれたこと——しかも、部室でもない場所で——に、なにか安堵のようなものを覚えた。
「あのさ」
林さんはわたしのほうを見て口を開く。
「カナメのこと、好きなの?」
「へっ……?」
予想だにしなかった質問に、わたしは思わず変な声をあげてしまった。
「えっと……、はい、えっと、人として、好きですよ……」
ふうん、と林さんはつまらなそうに呟く。
「でもまあ、それって恋愛感情だってことな気もするけどね。違うならすぐ否定するんじゃないかな」
「そ、そうですかね……」
「まあいいや。変なこと訊いて悪かった。気にしないで」
「は、はあ……」
林さんは顔を食事のほうへ戻して、茶碗を手にとり玄米をかきこむ。わたしも鮭の切り身の残りに手をつけた。
結局そのあとは一言も喋らないままに、二人とも黙々と食事をした。
「じゃあ、次の時間は講義あるし、また」
林さんはわたしより先に食事を終えると、そう言って食器の乗ったトレイを手に立ちさっていった。わたしは食事を続けながら、林さんの言った「カナメのこと、好きなの?」という言葉を、頭の中でぐるぐるともてあそんだ。
少なくとも、人としては好きだ。けれどそれが恋愛感情というものなのか、わたしにはよくわからない。恋人がいたことはないし、誰かに恋をしたという記憶もない。恋愛感情って、いったいなんなのだろう。
晴野さんの優しい微笑みが、わたしの脳裏をかすめる。そして、いつか指先がほんの少しだけ、晴野さんの手に触れたこと、そのときになぜかどぎまぎしたことを、思いだした。
8.
わたしは日記を書きおえて、四月始まりの手帳を開いた。来年の一月のマンスリーのページを開き、その七日のところに「晴野カナメさんの誕生日」と、赤いボールペンで書きこむ。
誕生日プレゼントを贈っても、迷惑にはならないだろうか。贈るとしたらなにがいいだろう。画材? 絵の具、筆、あるいはパレット……。いや、そういったものはもう持っているだろうし、晴野さんなりのこだわりだってあるだろう。画材はやめたほうがいい気がする。
なにか、使ってもらえるものがいいな……。食べたら無くなってしまうお菓子だとか、ただ机の上に飾るだけのオブジェだとか、そういったものではなく、日常的に使うようなもの。
ふと、自分の持っているボールペンに目をやる。高級なボールペン——あくまで、ボールペンとしては高級、という意味で——を贈ったら、晴野さんはそれを使ってくれるだろうか。でも、晴野さんがボールペンを普段使いしていなかったら、ボールペンを贈っても使ってもらえないかもしれない。わたしは、晴野さんが普段どんな筆記具を使っているのかすら知らない……。
多機能ペンならどうだろう。黒いインク一色のボールペンよりは、使ってもらえる可能性が高くなる……、ような気がする。来週の土曜日にでも文房具屋に行って、ペンを探そう。手元の手帳の今月のページを開いて、赤いボールペンから黒いボールペンへと持ちかえ、次の土曜日の欄に「文房具屋」と書きこむ。
手帳を閉じて、わたしは部屋の電気を消した。ベッドに身を横たえ、布団をかぶる。思いだそうとしたわけでもないのに、晴野さんの微笑みを思いだしてしまう。なんだか眠るのにいつもより時間がかかりそうだ、と思った。
早く眠りたいのに……。
布団にもぐってからどれだけ時間が経ったのだろう。体を起こして部屋の電気をつける。時計を見ると、まだ五分も経っていなかった。もう一度、部屋の電気を消す。
わたしはなにをしているのだろう。いったい、どうしたのだろう。
わたしは部室で、描きかけのキャンバスに向かっていた。イーゼルに立てかけた大きなキャンバスだ。キャンバスの下半分には、ビル群。ビルはどれも、地面の近くから崩れていっている。
絵の具の入っている箱を開けて、青と白の絵の具のチューブを手にとった。そしてパレットの上に青い色と白い色を出して、オイルで濡らした筆でその二つをかきまぜる。そうしてできた空色を、キャンバスの上のほうに伸ばしていった。
扉の開く音がしたので顔を向けると、晴野さんが入ってきてにっこりと笑った。
「やあやあ、この時間も講義ないんだ?」
「いや、ほんとうはあるんですけど、休講になっちゃって」
晴野さんはわたしの横まで歩いてきて、キャンバスに目をやる。
「おもしろい絵だね。なんだか少し寂しい感じもするけど」
「題して『ゲシュタルト崩壊』です」
わたしの言葉に、晴野さんは首を傾げる。
「わたし昔、ゲシュタルト崩壊のこと、ゲシュタルトっていうどこかの都市が崩壊していった事件のことだと思ってたんですよ」
「ああ、なるほど」
そう言って晴野さんは笑う。
「そうだ、今日はユウは来てないかな?」
「わたしは会ってないですね」
そっか、と答えながら晴野さんは部屋の後ろにある棚へと歩いていく。
「そういえばこの前、林さんが声かけてくれたんですよ。学食で」
「えっ?」
晴野さんはこちらを振りかえり、心底びっくりしたような顔をした。
「ユウが?」
「はい。えっと、どうしたんですか、そんなにびっくりして」
「いや、あいつが部室でもないところで、他人に自分から声かけるなんて、そんなの滅多にないと思うよ?」
「はあ……」
「それで、ユウに声かけられたのがそんなに嬉しかったの?」
「え、いえ、安心はしましたよ。林さんってその……、とっつきにくそうな印象があったから」
「ああ、まあそうだねえ」
晴野さんはわたしの答えに、どこかほっとするように笑う。そして体をくるりと回して、棚の前まで歩き、箱を一つ手にとった。
「どんな話をしたの?」
「えっと、コンテストの絵はどうかって訊かれて……」
「訊かれて?」
「あー、えっと……」
わたしは思わず言葉に詰まる。とはいえ、なにも言わないほうがまずいような気がしたし、かといって上手な嘘も思いつかなかった。
「晴野さんのことを、その、好きなんじゃないか、って言われて……」
「僕を?」
「は、はい……」
晴野さんは箱を手に、またこちらへと体を翻した。
「それで君は、なんて答えたの?」
「えっ……?」
どこか神妙な顔つきで訊ねられてまごついたわたしは、左手に持っているパレットに目を落とした。薄い青い色が夕日を受けて、粘りつくように照った。
「好きですけど、人として好きですけど、恋愛感情かはわからない、って……」
「そっかあ」
苦笑するように晴野さんは小さく呟く。わたしはパレットから目をあげて、晴野さんのほうに体を向けた。
「晴野さんは、誰かを好きなときに、それが恋愛感情なのかどうかって、わかりますか?」
「うーん……、まあ、なんとなくわかるよ」
晴野さんはわたしの問いかけに、困ったような声で答えた。そして箱を机の上に置いて画材をいくつか取りだし、パレットの上に絵の具を何色か出しはじめた。
「どうしたらわかるんでしょう?」
「え、なにが?」
こちらを見ることなく晴野さんは首を傾げて、筆を手にとりパレットの上で絵の具と絵の具を混ぜる。
「誰かを好きだと思ったときに、それが恋愛感情かどうかって、どうしたらわかるんでしょう?」
わたしは自分の体が少し晴野さんのほうへ乗りだしていることに気づいて、すっと姿勢を正した。
「さあ……。まあべつに、わからなくてもいいんじゃない?」
晴野さんはそう言って、右手に筆、左手にパレットを持ち、右端のキャンバスの前に立った。
「晴野さんは、今、誰か好きな人がいるんですか? 恋愛感情で好きな人が」
「えっ、どうしてそんなこと訊くのさ」
どこか慌てたような声で問われて、わたしは自分自身に対してまったく同じ疑問を抱いた。わたしはなぜ、そんなことを訊いたのだろう。
「いえ、なんとなく……、すみません」
「いや、謝らなくてもいいけど……」
晴野さんはそう言って、ふっと小さく息をつき、こちらを向いた。
「今までに誰かとお付きあいとか、したことないの?」
結局わたしの問いには答えることなく、晴野さんがそう投げかけてくる。
「ないです。誰かに恋愛感情を抱いたというような記憶も、ないんですよね」
「そっか。まあ、ユウが言ったことは気にしなくてもいいと思うよ」
「はい……」
それ、確か林さんも自分で言ってたなあ、とぼんやり思いながら、わたしはそれだけ答えた。
9.
何度も来たことがある文房具屋にいるというのに、わたしはなんだかそわそわしていた。今まではこんなにまじまじと見たことのないショーケースを覗きこむ。いろいろなペンが並んでいて、その横にはびっくりするような値段の書かれた札が置かれている。あくまでペンにしては高い、というだけのことなのだけれど、せいぜい数百円のボールペンしか買ったことのないわたしにとってはどれも、とてつもない高級品だった。
わたしは、小遣いはやるからバイトはせずに勉学に励め、と言った父の顔を思いだして、少し恨めしく思った。
ショーケースの中を端から端まで眺めて、また反対側まで視線を戻す。花びらや葉っぱの柄の入った軸のものもあるけれど、なんとなく晴野さんには単色のもののほうが似合うような気がした。
晴野さんは、何色が好きなんだろう。
わたしはまた、そんなことさえ知らないのか、と少し落胆する。ふっと、晴野さんに「青が好きなの?」と訊かれたことを思いだした。そして、晴野さんが描いていた青いひまわりを、思いだす。
透きとおるような——もちろん、実際には透きとおって中が見えているわけではないのだけれど——薄い青い色のペンが、わたしの目を惹いた。隣に置かれている値札には、わたしでも払えないことはないぐらいの値段と「三色ボールペン」という文字が並んでいる。
これなら……、普段はボールペンを使わない人でも、赤や青のボールペンなら、たまには使うんじゃないだろうか……。
今日は下見だけのつもりだった。晴野さんの誕生日までは、まだ何ヶ月もある。けれど、わたしは今すぐそれを買わなければいけないような気分になった。
あたりを見渡す。ちょうど少し離れたところで店員がしゃがんで、商品棚の下の抽斗を閉めようとしている。わたしはそちらへ歩みよった。
「あの、すみません」
「はい、お探し物ですか?」
その店員はぱっと立ちあがり、優しげな笑みを浮かべて少し首を傾げた。
「あの、そこのケースの中のペンが欲しいんですが……」
「承知しました、どちらのペンですか?」
そう問いながら店員は右手をエプロンのポケットに入れて、鍵を取りだした。
「その、真ん中あたりの、水色のペンを……」
店員はガラスのケースを開けて、ペンを取りだして持ちあげてみせた。
「こちらでしょうか?」
「はい、それをお願いします」
店員はにっこり頷いて、ペンを持ったままレジのほうへと歩きだした。わたしはその後ろを追いかけながら、鞄から財布を取りだす。
「プレゼントですか?」
レジの向こう側に回りこんだ店員が、カウンターの上にあるラミネートされた紙を指さした。そこには、ギフトラッピングの説明と何種類かの包装紙の写真が載っていた。わたしの目を惹いたのは、紺色の背景に黄色い星座が描かれた包装紙だった。
「これでお願いします」
「承知しました。それでは先にお会計いたしますね」
わたしがキャッシュトレイの上に札と小銭を乗せると、店員は釣り銭と小さな番号札をこちらへ差しだした。
「ラッピングが終わりましたらお呼びいたしますので、少々お待ちください」
はい、と答えてわたしは釣り銭と番号札を受けとり、レジの前から離れる。ギフトラッピングを頼んだことなどこれまではなかったから、待っている間どうしていればいいのかわからず、そわそわと近くの商品棚へと目をやった。いかにも高級そうな表紙のノートがあったのでその値札に視線を走らせ、この値段ではもったいなくて使えないだろうな、とぼんやり考える。
あまりレジから離れてはいけないのだろう、という気がして、その場からは動かずに他の商品棚へと視線を走らせる。いろいろなルーズリーフが並んでいて、晴野さんはノート派だろうか、ルーズリーフ派だろうか、と思いを巡らせた。
「ギフトラッピング三番でお待ちのかた、どうぞ」
声をかけられて振りむくと、先ほどの店員が包装された小さな箱を手に微笑んでいた。わたしは三番と書かれた番号札を渡してその箱を受けとる。
「ありがとうございます」
そうだ、高級なペンは安価なペンとは違って、箱に入れられるのだ……、とそんなことを今更に考えて、なんだか少し恥ずかしくなる。礼を言いながらも、足は店の出口のほうへと動きはじめていた。
10.
わたしは描きかけの「ゲシュタルト崩壊」と題した絵に、空色をじわじわと足していた。雲のない快晴の空。けれど一色で全体を塗りつぶすだけではつまらないように思えて、ほんの少しずつ色味を変えながら、空色を広げていく。背後に時折視線を感じたけれど、きっと気のせいだ、と自分に言いきかせながら。
今この部屋にいるのは窓際のキャンバスに向かっているわたしと、おそらく中央の机に向かっているであろう晴野さんだけだ。わたしがこの部屋に足を踏みいれたとき、晴野さんは椅子に座って机の上で水彩画を描いているようだったから。
「えっと……、東雲さん」
急に晴野さんの声が後ろから飛んできたのでわたしはびっくりして、はい、と裏返った声で答えてしまった。
「あ、急にごめんね」
「いえ、大丈夫です……」
なんだか心の底から申し訳なさそうに言われて、謝られても困ります、と心の中でつけくわえてしまう。むしろこちらこそごめんなさい、という気持ちになった。
「それで、なんでしょうか?」
「えっと……、土曜日、暇かな?」
「はい、今のところ特に用事はないですね」
わたしは体を反転させた。後ろから話しかけられながら絵を描くような器用さは、どうやらわたしにはないようだった。かと言ってわざわざ椅子に座るのもなんだかためらわれたので、とりあえず体だけ晴野さんのほうへ向けて、立ったまま答える。
「そっか……、えっとね」
晴野さんはわたしの顔を見ながらそう言って、いったん言葉を区切った。
「もしよかったら、一緒にランチとか、どうかな……? ちょっと、相談したいことがあって……」
「もちろんいいですよ。わたしでよければ喜んで」
予想外の誘いに、わたしの胸は勝手に弾んだ。晴野さんはほっとしたように笑う。
「よかった。駅前にお気に入りのお店があるんだけど、パスタは好き?」
「好きですよ」
「じゃあ、そこにしようかな。また連絡するから……、連絡先を訊いてもいい?」
わたしは、もちろんですよ、と答えて筆とパレットを机の上に置き、椅子に座ってジーンズのポケットから携帯電話を取りだした。晴野さんの手の中にはすでに携帯電話があったので、とりあえずわたしは自分の携帯電話の番号を口に出して伝える。晴野さんがそれを打ちこんで、ありがとう、と言う。
「じゃあ……、あ、電話かけたほうが早いか」
そう言って晴野さんが携帯電話の画面に触れると、わたしの携帯電話がほんの少しの間だけ震えた。着信履歴の一番新しいものを連絡先に追加して「晴野カナメ」と打ちこみ、「追加」のボタンに触れる。
「連絡待ってますね」
わたしの言葉に晴野さんは頷き、携帯電話をしまった。わたしも自分の携帯電話をポケットの中に戻して、筆とパレットを手にとって立ちあがる。キャンバスに向きなおり空色を広げようとして、筆を持つ手が少し震えていることに気づいた。
抽斗を開けて、手前の右側の隅にある、星座の描かれた包装紙にくるまれた箱を眺める。晴野さんの誕生日はまだまだ先だというのに、わたしはどうしてもうプレゼントを用意しているのだろう、と自分に呆れる。それから、晴野さんは喜んでくれるだろうか、という期待と不安の入りまじった気持ちを胸のうちにもてあそんだ。
抽斗の真ん中にあるノートを取りだして開く。昨日書いた日記の下に、今日の日付を書きこんだ。そしてさっきから頭の中にあった「晴野さんにランチに誘われた」という文章を、なるべく丁寧に、と思いながらも結局はいつものように走り書きした。相談があると言われたこと、携帯電話の番号を教えあったこと。
机の上に置いていた携帯電話が鳴ったので、右手にボールペンを持ったまま、左手でそれを手にとった。画面には「晴野カナメ」と表示されている。わたしは通話のボタンに触れた。
「はい、もしもし?」
「ああ、ごめんね、土曜日のこと、時間決めてなかったなって思いだして」
初めて電話越しに聞く晴野さんの声は、少し強張っているように感じられた。
「いつも、お昼ご飯は何時頃に食べてる?」
「日によってまちまちですね……。晴野さんの都合でいいですよ」
そっか、と晴野さんは呟いて、少しのあいだ黙った。
「じゃあ、十一時半でいいかな」
「はい」
「駅の北口で待ちあわせでいい?」
「大丈夫ですよ」
「じゃあ、十一時半に北口で」
わたしが、はい、と答えると晴野さんはまた少し黙った。楽しみにしてますね、と言おうかどうか迷っていると、晴野さんが口を開いた。
「楽しみにしてるね」
はい、と答える自分の声が少し裏返っていた。言おうと思っていたことを先に言われてびっくりしてしまったことが、電話越しに伝わってしまうのではないか、となぜか不安になる。
「じゃあね」
そう言われてわたしは携帯電話を耳から離し、画面を見てみる。まだ通話は切れていなくて、きっと晴野さんはこちらが通話を切るのを待つのだろう、とわかった。わたしはなんだか名残惜しいような気持ちで、通話を終了させるボタンに触れる。
ノートに新しく「夜、晴野さんから電話があった」と書きくわえる。それから手帳を取りだし、次の土曜日の欄に「十一時半、北口」とメモした。そして、もうすぐわたしは誕生日を迎えて、やっと十九歳になるのだ、ということを思いだす。そういえば晴野さんは何歳なのだろう。大学三回生なのだからおそらくは二つ上の二十歳だろう。けれど、浪人しているかもしれないから、確実にそうだとは言いきれない。晴野さんの穏やかな微笑みを思いだしてみる。少なくとも二十歳は超えているはずで、だとしたら「大人」なのだろうか。
いや、誰だって二十歳になったその日から突然大人になるわけではない。そう思いなおしてわたしはかぶりを振った。そもそも、どうしてわたしは晴野さんの年齢など気にしているのだろうか。
わたしはノートを抽斗の中へ、手帳を鞄の中へとしまい、部屋の明かりを落としてベッドの上に身を横たえた。まだ眠るには早いけれど、なぜだが一刻もはやく眠りたかった。目を閉じて、なにも考えない、なにも考えない、と頭の中で呟く。それに反して晴野さんの微笑みや青いひまわり、そしてほんの少しだけ指先が触れたときの感触が脳裏に浮かんでは消えていった。
11.
「今日はありがとう。東雲さん、えっと……」
駅の近くにあるレストラン——晴野さんが「お気に入りのお店」と言っていたパスタの店——の隅にあるテーブルに、晴野さんとわたしは向かいあって座っていた。晴野さんはこちらを見ながら、言葉を続けるかどうかを迷っているようだった。
「いえ、どうしました?」
「いや、えっと……、アリカちゃんって呼んでも、いいかな?」
続きを促すと晴野さんは少し心配そうな顔でそう問いかけてくる。
「もちろんです。じゃあ、わたしは……、カナメさんって呼んでもいいですか?」
「うん、むしろそれが嬉しいな」
カナメさんはぱっと顔を明るくして頷いた。
それからテーブルの真ん中に置いてあったメニューを開き、こちらへ向ける。
「好きなの選んで」
「うーん、カナメさんはなんにするんですか?」
「僕はカルボナーラ。いつもここではカルボナーラを食べてるんだ」
そう言ってカナメさんはメニューの下のほうに書かれている「カルボナーラ」という文字を指さした。
「じゃあ、わたしもそれにします」
「いいの? 他にもいろいろあるし、ゆっくり選んでいいんだよ?」
「いいんです、わたしもここのカルボナーラを食べてみたいです」
そっか、と言ってカナメさんはメニューをテーブルの端に置き、近くのテーブルを拭いていた店員のほうに向かって少し手を挙げた。
「はい、お決まりでしょうか?」
「カルボナーラを二つ、お願いします」
店員がやって来て訊ね、カナメさんがそれに答える。
「お飲みものはどうされますか?」
カナメさんが、しまった、というような顔をする。
「すみません、すっかり忘れてました……。アイスコーヒーと……、アリカちゃんはなにがいい?」
店員からわたしへと視線を滑らせて、カナメさんがまたメニューに手をのばす。
「わたしもアイスコーヒーで」
「承知しました」
店員が去っていくと、カナメさんが不安そうに口を開いた。
「よかったの? ごめんね、先に訊いておけばよかった……」
「いいんですよ、わたしコーヒー好きですから」
答えながらわたしは、自主性のない人だ、と思われていたらどうしようかと少し心配する。パスタも飲みものも、カナメさんとは違うものを自分で選ぶべきだっただろうか。けれどそれ以上に、カナメさんがいつも食べていつも飲んでいるものの味を知りたいと思っていたのだ、ということに気づく。
「まあ、それならいいんだけど……。そういえば、アリカちゃんは一人暮らし?」
「いえ、実家にいます。カナメさんは?」
「僕は一人暮らしだよ。けっこうな田舎から出てきたからね」
カナメさんはそう言うと、鞄の中から青い包みを二つ取りだした。
「まだちょっと早いけど、お誕生日おめでとう。これ、プレゼント」
テーブルの上に青い直方体と立方体が並べられる。
「ありがとうございます……! わたしの誕生日、覚えててくれたんですね」
わたしは青い包装紙に包まれた二つの箱を手にとってみた。
「もちろんだよ」
「これ、今開けてもいいですか?」
「うん。気に入ってもらえるか、わからないけど……」
はやる気持ちを抑えて、まず直方体の包装紙を丁寧に剥がしてみる。中から出てきたのは黒い箱だった。箱を開けると、そこには深い青色のペンが一本入っていた。
「アイスコーヒーです」
「あ、ありがとうございます」
先程と同じ店員がトレイにアイスコーヒーの入ったグラスを二つ乗せて、テーブルの傍に立っていた。カナメさんが礼を言うと、店員はにっこり笑ってグラスを二つテーブルの上へ移動させて、また立ちさっていった。
わたしは手元の箱の中のペンに視線を戻す。
「それ、万年筆だよ。持ってるかもしれないけど……」
「いえ、万年筆なんて初めてです」
「そっか。万年筆で落書きっていうのもなかなか楽しいよ。よかったら使ってみて」
「ありがとうございます」
初めて目にした万年筆をおそるおそる手にとって、まじまじと見つめる。ふと、軸の端のほうに「A.S」と刻まれていることに気づいた。
「これ……、もしかして、わたしのイニシャルですか?」
「そうだよ。えっと……、余計なお世話だったらごめんね?」
「どんでもないです、すごくうれしいです」
わたしの答えにカナメさんは、ほっとしたように笑う。万年筆を箱に戻し、その箱を閉じてテーブルの脇へやり、もう一つの青い包みを手にとってみる。
「そっちはインク」
ゆっくり包装紙を剥がすと、紙でできた箱が出てきた。箱を開けてその中にあった小さな瓶を取りだしてみる。瓶の中には、こちらもまた深い青色の液体が入っていた。
「青が好きなのかなって思って……」
カナメさんが照れるように言ったので、いつか「青が好きなの?」と訊かれたことを思いだした。そういえば、そのときわたしはなんと答えたのだろう。脳裏にカナメさんの描いていた青いひまわりの絵が浮かんでいたことは覚えているのに、自分がどう答えたのかは思いだせない。
「はい、青、好きです」
ほんとうは、それほど青が好きというわけではなかった。いや……、今は好きだ。カナメさんの描いていた青いひまわりを見たあのときから、わたしは青という色に強く惹かれるようになった。それを打ちあけたら、カナメさんはどんな反応をするだろうか。気にはなるけれど、やっぱり恥ずかしくて言えない。
「よかった」
カナメさんはほっとしたように微笑む。
「綺麗ですね、この青……。なんか、深くて」
「深海、って感じじゃない? 僕はその色、海みたいだなあって思って」
改めて万年筆を眺めながらわたしが言うと、カナメさんは楽しげにそう答えた。海……。
そうだ、海に行きたい。カナメさんと一緒に、海に行きたい……。わたしはぼんやりと、そんなことを考えた。
カナメさんがわたしではないどこかに目を向けて、あっ、というような顔をした。振りかえると店員がトレイを持ってすぐ傍までやって来ていた。とりあえずわたしは瓶を箱に戻して、テーブルの端に置く。
「お待たせいたしました。カルボナーラ二つです。ご注文はお揃いですか?」
パスタの盛られた皿をテーブルの上に置いて、店員がにっこりと笑う。
「はい、ありがとうございます」
カナメさんが答えると店員は、ごゆっくりどうぞ、と言いのこして立ちさっていった。
「じゃあ、食べようか」
フォークを手にとってカナメさんが微笑んだ。
12.
「あの、ところで相談ってなんですか?」
カルボナーラを食べおえてアイスコーヒーを啜り、わたしはカナメさんの顔を見ながら訊ねる。
「あー、いや、なんだったかなあ」
カナメさんはそう言って笑った。わたしは思わず首を傾げる。
「えっと、もし嫌じゃなかったら、だけど……、家に来ない? ほら、前に僕のギター聴きたいって言ってたからさ……」
カナメさんが少しずつ言葉を選ぶように、そう言った。
「ぜひ聴かせてください」
わたしがそう答えると、カナメさんはなぜか少し困ったように笑う。
「うん、じゃあ……、行こうか」
わたしがアイスコーヒーを飲みおえると、カナメさんが立ちあがった。わたしも立って、レジに向かうカナメさんの後ろをついていく。カナメさんは二人分の食事代を払って、店を出た。
「半分払いますよ」
「いいよいいよ、僕のほうがちょっとだけだけど、年上なんだし」
こういう場合、奢ってもらうべきなのか、それとも自分の分は無理を言ってでも払うべきなのか、わたしにはさっぱりわからなかった。ただ、せっかくの好意を無下にすることがためらわれて、わたしは軽く頭を下げる。
「ありがとうございます。それじゃあ、お言葉に甘えて……」
カナメさんは、うんうん、と頷いて歩きはじめた。
「あの……、カナメさんって、おいくつですか?」
「二十一だよ」
訊いてよかったのかよくなかったのか、わたしは少し混乱する。カナメさんは一月生まれだから、まだ誕生日を迎えていない。それなのにわたしの三つ上で……、ということは?
「ああ、三回生なのになんで、って顔してるね」
「え、いえ……」
少しこちらを振りかえったカナメさんにそう言われて、わたしは慌てて否定する。カナメさんはいつもどおりに微笑んでいた。
「まあ、ちょっとね。ああ、ここの二階だよ。二〇五号室」
少し古そうなマンションの前で、カナメさんがそう言った。そして壁にはまっているパネルに鍵を差しこんで、開いた自動ドアをくぐっていく。わたしは、もう着いたのか、と思いながらその後ろに続いた。階段を昇って二〇五号室の前に来る。カナメさんが今度はドアノブの下にある鍵穴に、鍵を差しこんで回した。
「さあどうぞ」
扉を開いて押さえ、カナメさんはわたしを先に上がらせた。
「失礼します」
わたしはそう言いながら靴を脱いで玄関に揃えた。狭い。八畳ぐらいの、これがおそらくワンルームというものなのだろう。玄関のすぐ傍にキッチンがあり、部屋もここから見えている。部屋の片隅にギターが立てかけられていて、ギターだ、とわたしは胸の中で呟いた。
カナメさんがわたしを追いこして部屋の奥へと進んだ。部屋の真ん中には小さな低い机があって、その手前に一つ、薄い青色のクッションが置いてある。ここに座って、と言いながらカナメさんがそれを指さしたので、わたしはそこまで歩いていき、おそるおそるクッションの上に正座をした。
わたしを見ながら、カナメさんはおかしそうに笑った。
「そんな、なにも正座しなくても」
「そ、そうですよね……」
なんだか恥ずかしくなって、慌てて足を崩す。左にはベッドがあり、カナメさんはその真ん中あたりに腰かけた。その奥に、先程わたしの目を惹いたギターがある。それから右のほうには小さなテレビがあって、机の上にはノートパソコンと数冊の本とノート、そしてペンが散らばっている。わたしは思わずもう一度、あたりを見回した。
「どうしたの?」
「いや、キャンバスとか、ないんだなって……」
「ああ、僕は家では絵は描かないんだ」
「どうしてですか?」
「うーん、どうしてだろうねえ」
自分でもわからないのか、それともわかっているけれど教えたくないのか、カナメさんは曖昧に笑いながら首を傾げてみせる。そして立ちあがってギターを手にとり、またベッドに腰かけた。一本ずつギターの弦を指で弾いて、時々ギターの先端にあるネジのようなものを回す。
「アリカちゃんは、楽器とかはまったく?」
「経験ないですね」
「そっか。今チューニングしてるんだ。ちょっと久しぶりだからね」
さすがにチューニングという言葉は聞いたことがあるけれど、それとこれとがどう関係あるのか、よくわからなかった。
「えっと、その、ネジみたいなのを回すと、どうかなるんですか?」
「えっとね、これをこっちに回すと音が高くなって、反対に回すと低くなるんだ」
そう言いながらカナメさんはネジを回した。
「六個あるでしょ。弦一本に対して一個。これを回すと弦が緩んだり、えっと……、なんていうのかな、張りつめるっていうか……」
「ああ、わかりました。そういうことですね」
言葉を探すカナメさんに、わたしは口を挟んだ。いつか物理の授業で教わった、弦の伸び縮みと音の高低についての関連性を思いだしたから。正直、どちらが高くてどちらが低いのかをすぐには思いだせなかったけれど、それはどうでもいいことのように思えた。
話しているうちにチューニングは終わったらしく、カナメさんは身を乗りだして、机の上にある茶色くて楕円形をした缶に手を伸ばした。そして器用に片手でその蓋を開ける。その中から、またわたしの知らないなにかを取りだして、それでギターの端のほうを挟んだ。
「これはカポタストって言うんだけど、えっと……、どう説明したらいいかな。ここをずっと押さえてる状態を作りだすんだ」
「はあ……、そうするとどうなるんですか?」
「えっとね……、難しいな。まあ、ラクになるんだ。あとは同じ曲でも、全体的な音の高さを変えられるし」
「へえ……」
まったくなにがなんだかわからなかったが、きっとわからなくても大丈夫だろう、と思って適当に相槌を打つ。カナメさんはギターを抱えなおして、右手を少し丸めて上から下へと振った。じゃらん、と音がする。そしてカナメさんは右手を広げて、六本の弦を覆った。ぴたりと音がやむ。
「じゃあ、一曲弾かせていただきます」
カナメさんはおどけるようにそう言ってから、すっと真顔に戻る。カナメさんの左手は弦を押さえる指を次々と変えてゆき、右手がリズミカルに上下に振られた。まったく聴いたことのない曲がゆっくりと進んでいく。カナメさんは歌う様子がなく、これは歌詞のない曲なのだろうか、それともあるけれど歌わないだけなのだろうか、とわたしはぼんやり考える。
やがてギターの音はだんだんと小さくなり、そして消えた。カナメさんがこちらを向いて、どうかなあ、とでも言うように微笑む。
「すごい……、ギター一本でこんなにいろんな音が出るなんて、知りませんでした」
「まあ、弦が六本あるからね」
「初めて聴いたんですけど、なんていう曲なんですか?」
カナメさんはカポタストを外しながら口を開く。
「僕の大好きな曲……、『デクレッシェンド』っていう曲なんだ。前に見せた絵のタイトルに使わせてもらっちゃった」
そう言ってカナメさんは恥ずかしそうに微笑んだ。
「そうだ、君が知ってる曲でなにか弾けるのあるかな……。普段どんなアーティスト聴くの?」
その曲には歌詞はないんですか、と問いかけようか迷っていると、カナメさんがそう言ってわたしの顔をのぞきこんだ。わたしがぱっと思いついたバンドの名前を挙げるとカナメさんは、そのバンドならあのバラード曲がいいかも、と呟きながらまたギターを弾きはじめた。たしかにそれはわたしが何度も聴いたことのある曲だった。けれどカナメさんはやっぱり歌わなかった。この曲には歌詞があるのに。
「歌わないんですか?」
ギターの音がやむと、わたしは思わずそう訊ねた。
「うん、僕は歌が上手じゃないんだ。歌ってほしかった?」
「え、いや、まあせっかくなら聴いてみたかったかなって……」
カナメさんは、そっかあ、とどこか間延びした声で答えながら、カポタストを缶に戻して蓋をして、ギターを壁際 ̶̶そこにはさっきまで気がつかなかったが、ギターを立てておくための黒い棒のようなものがあった ̶̶に立てかけた。
「そういえばアリカちゃん、万年筆は初めてって言ってたよね」
「はい」
「じゃあ、インクの入れ方教えておかないとね」
わたしはカナメさんに促されて、鞄から万年筆の入った箱と、インクの瓶の入った箱を取りだした。箱を開けて万年筆と瓶を出し、机の上に置く。
「カートリッジっていうのを使えばすぐに書けるしラクだけど、いろんなインクを使うならコンバーターっていうのを使わなきゃいけないんだ」
カナメさんはベッドから降りて床にあぐらをかき、机の上の万年筆を手にとる。そしてそのキャップを外してから、軸の真ん中あたりをくるくると回した。万年筆は二つに割れて、その中には透明な細い管のようなものが入っていた。
「これがコンバーター。こうやって外せるよ」
カナメさんがコンバーターを軸から引きぬき、そしてまた元に戻す。
「こうやってつけた状態で……、インクの瓶の蓋、開けてみて」
わたしはインクの瓶を左手に持ち、右手でその蓋を回した。そして瓶をカナメさんの手の近くに置く。
「ペン先をインクに浸して、ここを回すんだ」カナメさんがコンバーターの先端にあるネジのような部分を回すと、少しずつコンバーターの中に深い青色が入っていった。
「へえ……、すごい……」
わたしは思わず呟く。
「インクは手につくとなかなか落ちないから、気をつけてね」
そう言ってカナメさんは机の上にある、いろんな色の染みのついた布でペン先を拭った。そして二つに分かれていた万年筆をくるくると回して、一本に戻す。
「これで書けるようになったよ。ほら、書いてみて」
カナメさんは万年筆をわたしに差しだして、机の上にあったノートを一冊開いてわたしの前に置いた。
「これに書いちゃっていいんですか?」
「いいよ。落書き帳みたいなものだから」
わたしはなにを書こうかと考える。絵だろうか。いや、それは恥ずかしい。少し震える手を落ちつかせて、万年筆を持ちなおす。
——ありがとう。
わたしはノートにそう書いていた。ほとんど無意識に。
「それって、僕に対して?」
カナメさんが少しびっくりしたように言う。
「えっと、はい、あの……」
わたしはなんだか恥ずかしくて声を詰まらせた。カナメさんが、ふふ、と笑ってわたしの手から万年筆を取る。そして今わたしが書いた言葉の下に、ペン先を走らせた。
——どういたしまして。
そう書いて、カナメさんは万年筆のキャップを閉め、わたしに手渡す。
「えっと、インクの入れ方、ありがとうございました。これ、すごく書きやすいですね」
「まあ、それなりのものだからね……。いや、そんなに高いわけじゃないけどね」
わたしは受けとった万年筆を箱に戻して、インクの瓶の蓋を閉めてそれも箱に戻す。
「カナメさんは……、いつも、万年筆を使ってるんですか? 講義のノートとかも?」
「いや、ボールペンも使うよ。そのときの気分次第」
カナメさんの答えに少しほっとして、そうなんですね、と頷く。カナメさんは床から立ちあがって、キッチンへと移動した。
「コーヒーでも飲む?」
「はい、お願いします」
カナメさんはコンロの上にポットを置き、コンロの火を点けて、棚からコーヒー豆を挽いた物らしき粉の入った瓶を取りだした。わたしはそこまで見届けてから、机の上に視線を戻して、カナメさんが落書き帳のようなものだと言ったノートを閉じる。それから、机の上にある数冊の本に目をやった。どれもカバーはされておらず、作品名と作者名が見えている。どの作品も作者も、わたしの知らないものだった。タイトルからすると小説のように思えたけれど、もしかしたら違うかもしれない。
「カナメさんは、本を読むのが好きなんですか?」
わたしはなんとなく、キッチンにいるカナメさんに向かって問いかけた。
「うーん、まあ、好きかなあ。そんなに読書家ってわけじゃないけどね」
ポットが熱されて音を立てはじめる。
「アリカちゃんは?」
「わたし本はあんまり読まないんですよね……。最近は特に、数学書ばっかりで」
「数学書? 理学部なのは知ってたけど、アリカちゃん数学科なの?」
「そうですよ」
ポットが静かになり、それからコーヒーの香りが漂ってきた。カナメさんが、へえ、と相槌を打つ。
「どうして数学科に入ったの?」
しばらく黙ってコーヒーを淹れていたのであろうカナメさんが、両手に一つずつマグカップを持って、ベッドに腰かけながらそう訊ねる。そして身を乗りだして片方のマグカップをわたしの前に置いた。
「どうぞ」
「ありがとうございます。えっと、数学が好きで……」
「なんで?」
カナメさんは、ただただ不思議、といった顔でこちらを見る。
「曖昧なのが、好きじゃないんです。数学の世界って、十進数が前提なら、一足す一は必ず二になるじゃないですか」
「一足す一が二にならない世界もあるの?」
またカナメさんは、ただただ不思議、といった顔をする。
「あー、えっと、そうなんです。普通は二ですけど、二進数の世界なら一足す一は十だし……」
わたしはどう説明たものかと考えあぐねる。カナメさんはコーヒーを一口啜って、呟いた。
「なんだかそれなら、数学の世界もずいぶんと曖昧な気がするけどなあ」
わたしは思わず、うう、と小さくうめいた。
「ごめんごめん、ちょっといじわるしたくなっちゃった」
そう言ってカナメさんは楽しそうに笑った。わたしは目の前にあるマグカップを手にとって、口をつける。
「あ、ミルクとかお砂糖とか、いらなかった?」
「はい、いつもブラックで飲んでるので」
「そっか、大人だねえ」
からかうようにそう言って、カナメさんがまたコーヒーをすすった。
「僕はね、曖昧でよくわからない人間の感情、けっこう好きだよ」
どこか独り言のようにそう言って、カナメさんはコーヒーを二度三度とすすった。そしてわたしの顔をのぞきこむようにして黙りこむ。わたしは思わず首を傾げた。
「君は、僕を好きだと言ってくれたよね。恋愛感情かどうかは、わからないみたいだけど」
「えっと、はい……」
改めて言われて、わたしはまごつきながら頷く。カナメさんは優しく微笑んで、言葉を続けた。
「恋愛感情かどうかわからない、そんな曖昧な感情だとしても、僕はうれしいよ」
わたしは思わずカナメさんから目をそらして、コーヒーを一気にあおった。まだ熱いけれど、その熱がわたしの恥ずかしさを少し、打ちけしてくれるような気がした。
「僕だって、恋愛感情とはなにか、なんて訊かれても、よくわからないし」
カナメさんはそう言って笑う。
「そう、なんですか?」
「そうだよ。そんなものだよ」
思わず訊ねるわたしに、カナメさんはそう答えて、またこちらをじっと見た。
「うーん……」
心底困ったような微笑みを浮かべながら、カナメさんがうめく。
「どうしたんですか?」
「いやあ、なんでもないよ……? コーヒー飲んだら帰る?」
「そうですね、あんまりお邪魔しちゃ悪いですし」
「悪くないんだけどね……、まあ、でも……」
ごにょごにょと最後のほうが聞こえなかったので、なんですか、と問いかけたけれど、カナメさんは答えなかった。そしてコーヒーをすする。
「駅まで送るよ」
突然そう言って、カナメさんはマグカップを机の上に置き、わたしの手にあるマグカップを覗きこむ。わたしの持っているマグカップは、もうからっぽだった。カナメさんの持っていたマグカップに目をやると、まだ半分はコーヒーが残っていた。わたしはなんとなく、それを見なかったことにした。
「はい、ありがとうございます」
立ちあがって玄関に向かうカナメさんの後ろをついていく。玄関を出て、カナメさんが鍵を閉めて、駅のほうへと歩く。お互いに黙ったまま、あっという間に駅についた。
「じゃあ、気をつけて。今日はありがとうね」
改札のすぐ前で、カナメさんがそう言った。わたしは財布からICカードを取りだしながら、カナメさんのほうへ少し頭を下げる。
「こちらこそ、ありがとうございました」
わたしは改札を抜けて少し歩いて、振りかえってみた。カナメさんはまだ同じ所に立ってこちらを見ていた。どこか寂しそうに見えるのは、わたしの気のせいだろうか。わたしはふと思いたって、右手を大きく挙げて振ってみせた。カナメさんは少しびっくりしたような顔をして、それから右手を軽く振ってくれた。カナメさんの口が動いたけれど、なにを言ったのかはわからなかった。
13.
「はあ……」
箸を持つ手をとめて、ホツエがどこかうっとりしたようなため息をつく。
「なに、恋でもしたの?」
シズエが箸を口元へ動かしながら、そう訊ねる。
「えー、なんでわかったの?」
少し笑いながらホツエが訊ねかえす。
「わかるよ。ね、アリカ」
「いや、わたしはわからなかったけど……」
「まあ、アリカは鈍いもんねえ。で、誰なの?」
シズエは笑って、ホツエにまた訊ねる。
「多分、シズエは知らない人だよ」
「ってことは、アリカは知ってる人?」
「あー、うん……」
ホツエは困ったように、けれどどこか嬉しそうに頷く。
「私が知らないってことは、美術サークルの人じゃないのか」
シズエは呟きながら茶碗を左手にとった。
「アリカは心当たりある?」
「まったくないけど……」
シズエに問われてそう答えながらわたしは、ホツエとわたしの共通の知りあいを何人か思いうかべてみた。けれど、ホツエが誰かと特別に親しくしているところは、思いだせなかった。
「三谷先生だよ」
ホツエの口から飛びだした名前に、わたしはびっくりして箸を取りおとしそうになった。
「三谷先生?」
シズエは少し興味を失ったように訊ねた。
「そう、解析入門の先生なの」
「なに、それ」
「数学だよ、微分とか積分とか」
「あー、数学の先生ってことか。じゃあ知らないや」
シズエはそう言って、食事を続けた。
「なんでまた三谷先生……?」
わたしは思わずホツエのほうを見ながらそう訊いた。
「なんでって言われても」
ホツエは三谷先生に遅刻を注意されているし、いい印象を抱いているとは思えなかった。
「すごく優しいんだよ。毎週先生のところに行って質問してるんだけどさ。告白したいなあ」
ホツエはまた、どこかうっとりしながら言う。
「すればいいじゃん、多分振られるけど」
シズエが口を挟むと、ホツエは少し眉をひそめてそちらに顔を向けた。
「なんで?」
「だって教員と学生って、ねえ?」
シズエはそう言って、わたしのほうを見ながら首を傾げてみせる。
「まあでも大学生だし、それはいいんじゃないかな……?」
なんとなくわたしがフォローを入れると、ホツエは顔を輝かせながら口を開いた。
「そうだよね。もう子どもじゃないもんね」
「あー、いや、それは多分子どもだと思われてるけど……」
いつか三谷先生が言っていた「大人というには幼い」という言葉を思いだして、一応そう言ってみたが、ホツエは聞いていないようだった。
「アリカ、明日ついてきてよ」
「え?」
「だから、三谷先生に告白しに行くから!アリカも一緒に!」
「な、なんで……」
「だって心細いもん。もしかしたらダメかもしれないし」
「まあダメだろうね」
少し顔を曇らせたホツエの隣で、シズエはいたずらをする子どものように笑いながら口を挟む。
わたしは誰かに告白とやらをしたこともないし、誰かに告白とやらをされたこともないけれど、おそらくそういった場に第三者がいるのは居心地が悪いだろう、ということぐらいは想像がついた。
「とにかく、明日の六限が終わったら、ね!」
そう言ってホツエがこちらを見て目を輝かせたので、わたしはなにも言えずに頷いた。シズエが、せいぜい頑張りな、と言って楽しそうに笑った。
「先生」
三谷先生の研究室に入るなり、ホツエは少し強張った声を発した。
「珍しいですね、今日は東雲さんもですか」
わたしは椅子に座っている三谷先生に向かって、こんにちは、と軽く頭を下げる。
「先生って結婚はされてるんですか?」
「いいえ、していませんよ」
ホツエの問いに、三谷先生は静かに答える。
「じゃあ、恋人は?」
「いません」
「それじゃあ……」
「申し訳ありませんが」
言いかけたホツエの言葉を、三谷先生は遮る。
「えっ、私まだなにも言ってませんよ?」
顔を赤くしてホツエが焦る。
「あのですね、あれだけこの部屋に足を運んで、結婚しているのか、恋人はいるのか、と訊かれれば、よほど鈍い人間でなければなにを言いたいのかはわかりますよ。どうして友人をその場に同席させようというのかは、理解しかねますがね……」
ホツエは少し黙りこんでから、ふっ、と息をつく。
「どうしても、心細くて……。でも、なんでダメなんですか?わたしがまだ子どもだからですか? それとも学生だから?」
「両方に加えて、僕があなたに恋愛感情を抱いていないからですよ」
三谷先生の言葉にホツエは、うう、とうめいた。
「わかったら帰ってください」
「先生」
わたしが突然声をあげたので驚いたのだろう、三谷先生がこちらを見て首を傾げる。
「自分でそれが恋愛感情かどうかって、わかるものなんですか?」
「なんですか、突然」
「わたし、わからないんです。好きな人はいるけど、それが恋愛感情かどうか」
三谷先生は、はあ、と大きく溜息をついた。
「えっ、アリカ好きな人いるの?」
ホツエはびっくりしたようにこちらに顔を向ける。
「どうしてそれを僕に訊くんですか」
「いえ、さっきホツエに対して恋愛感情を持ってないって、断定したから……」
「じゃあですね、東雲さん、あなたは僕に恋愛感情を抱いていますか?」
思わぬ問いかけにわたしは固まった。
「アリカの好きな人って三谷先生なの?」
「いや、違うよ?」
ホツエに問われて、わたしは慌てて否定する。
「つまりあなたは、僕に対して恋愛感情を抱いていないと、自分でわかるのでしょう」
机を人さし指で軽く叩きながら、三谷先生がそう言った。
「えっと……、たしかに……。いや、でもそうじゃなくてですね、恋愛感情でないことはわかるかもしれないですけど、恋愛感情であることもわかるのかなって……」
三谷先生は大仰に溜息をついた。
「それは白崎さんに訊いたらいいでしょう。僕に恋愛感情を抱いていたそうなので」
「なんで勝手に過去形にするんですか」
ホツエは、三谷先生の言葉に食ってかかる。
「そうしてもらわないと困るからですよ。あなたにはちゃんと、あなたに相応しい人が現れます」
「それが先生じゃないなんて、言い切れないじゃないですか」
「言い切れますよ……」
一度そこで三谷先生は言葉を区切った。
「申し訳ありませんが、正直に言って疲れました。二人とも、帰ってください」
14.
「ねえ、アリカがさっき言ってた好きな人って誰なの? 私も知ってる人?」
研究室を出るなり、ホツエは目を輝かせて訊ねてくる。三谷先生のことはもういいのだろうか、などと少し思ってしまった。
「えっと……、恋愛感情かはわからないよ?」
「誰なの?」
なんだかわたしはそれに答えたくなかった。どうしてなのかは、自分でもよくわからなかったけれど。
「秘密」
「えー、ずるいよ。私が好きなのは三谷先生だって、教えたのに」
「教えてなんて頼んでないよ?」
「そ、そうだけど……」
ホツエは少しバツが悪そうに答える。
「それよりホツエは、三谷先生を好きだっていうのが恋愛感情だって、どうしてわかるの?」
「え……、どうしてだろう?」
ホツエは立ちどまって首を傾げた。
「どうしてって言われると難しいなあ。でもわかるものは、わかるよ?」
わかるものは、わかる。それならやっぱり、わたしのこの「好き」は、恋愛感情ではないのだろうか。
「アリカは難しく考えすぎなんじゃないかな。好きなものは好きだし、なんならそれが恋愛感情かどうかって、いちいち迷う必要もないんじゃない?」
「うーん……」
たしかに言われてみれば、どうしてわたしは自分の気持ちが恋愛感情なのかどうかを、こんなに気にしているのだろう、という気もしてくる。それでも、いつか林さんに言われた「それって恋愛感情だってことな気もするけどね」という言葉を思いかえして、なんだかもやもやした気持ちにもなった。
「好きって言われて嫌な気持ちになる人なんてそうそういないでしょ。その気持ちだけでも、伝えてみれば? もしかしたら初めての恋人ができるかもしれないし!」
またホツエが目を輝かせながら、そう言った。三谷先生はホツエに好きだと伝えられて——というより伝えられることを察知して——嫌な気分……、とまではいかなくても、困っていたのではないだろうか、と思ったけれど、さすがにそれを言うのは酷な気がした。
「そう、だね……」
とりあえずそう答えてはみたけれど、わたしはきっとホツエの助言には従わないだろう、ということも、なんとなくわかっていた。
部室に入ると、窓際のキャンバスの前に立っていた林さんがこちらに顔を向けた。こんにちは、と声をかけてわたしは部屋の後ろの棚へと歩いていく。
「カナメと付きあってんの?」
「へっ?」
林さんの言葉に、わたしは素っ頓狂な声を出してしまった。
「いえ、お付きあいしているわけじゃないですけど……。どうしてですか?」
「土曜日、駅前のパスタの店にいたろ。二人で」
「ああ……。相談に乗ってほしいって言われて……」
わたしの言葉に、林さんは首を傾げる。
「相談? なに相談されたの」
そういえば、結局なにかを相談されたわけじゃない、ということを思いだす。
「えっと、なにも相談されなかったですね……」
ふうん、と林さんが呟く。
「あんたと二人で過ごすための口実ってことか」
「あ、でも、誕生日プレゼントをもらったんです」
口実、という言葉になんだかわたしはどぎまぎして、言い訳を述べているような気分になりながら、慌てて言葉を並べる。
「へえ」
林さんはどこか面白くなさそうに相槌を打った。
「で、それだけ?」
わたしはそう訊かれて、言葉に詰まる。
「家に連れこまれたり、したんじゃねえの」
「連れこまれてなんか……、わたしがギター聴かせてほしいって言ったから、それならおいでよ、って……」
「なに、あいつのギター聴いたの?」
林さんがもはや険悪といってもいいくらい、低い声で問いかける。
「え、はい……」
部屋の扉が開いたので目をやると、カナメさんが入ってくるところだった。
「俺には聴かせてくれないよな」
カナメさんのほうへ目を向けて、林さんがそう言った。
「え?」
「ギターだよ」
きょとんとするカナメさんに、林さんがそう答える。
「お前らが駅前の店で飯食ってんの、たまたま見かけたんだよ」
「そうなの?」
林さんとカナメさんのやりとりをよそに、わたしはなにか言ってはいけないことを言ってしまったのだろうか、と不安になっていた。そんな自分の気持ちをごまかすような気分で、棚から箱を一つとって机の上に置く。箱を開けて画材を取りだし、油彩用のパレットの上に絵の具を絞りだす。
「それで……、僕の家でギター弾いて聴かせたのを、アリカちゃんに聞いた、ってこと?」
しばらく黙っていたカナメさんがそう言うと林さんが頷きながら口を開いた。
「いつの間にか呼び方も変わってるし」
「あ、うん……」
カナメさんは困ったようにそう答えて、机の上の画材を触るともなく触る。
「お前らの曖昧な態度見てると……、正直イライラする。勝手なこと言ってるのは、わかってるんだが」
わたしは顔をあげて林さんのほうへと目を向けた。林さんはキャンバスに背を向けて、腕組みをして憮然としていた。
「そりゃ、俺の想いが叶うなんて、思ってねえけど……」
林さんがしりすぼみにそう言葉を続けると、カナメさんは手元から目をあげて林さんのほうを見た。
「え、ユウの想い、って……」
どこかわざとらしく、林さんは溜息をついてみせた。
「俺はお前が好きなんだよ、カナメ」
「僕?」
心底びっくりしたように、カナメさんが声をあげる。
「あ、ありがとう。でも……」
カナメさんが言葉を続けようとすると、林さんはふっと息をついて口を挟んだ。
「わかってるよ」
カナメさんの言葉を遮って、林さんが寂しそうに笑いながら言った。そしてまた、小さな溜息をつく。
「帰るわ……」
林さんは呟くようにそう言って、画材を片付け、部屋を出ていった。扉が閉まったのを確認して、わたしは口を開く。
「あの、林さんが言ってたんですけど……、相談があるって言ってたのは、その……」
わたしは「口実」という言葉を口から出そうとしたけれど、喉がつっかえたような息苦しさを覚えた。
「君に外で会いたかったからさ、ただの口実だよ」
カナメさんは少し困ったように微笑みながら、そう言った。
「ユウもそう言ってた?」
「はい……」
あはは、とカナメさんが乾いた声をあげる。
「僕はね、君が好きなんだ」
急に真面目な顔になったカナメさんにそう言われて、わたしは思わず体を硬くした。いったい「好き」という言葉にどう対応すればいいのか、わからなかった。
「あ、ありがとうございます……」
わたしが絞りだしたその言葉に、カナメさんはどこか寂しそうに微笑んだ。
「ごめんね。困らせちゃったかな」
「いえ……。その、わたし、恋愛感情っていうものが、よくわからなくて……」
カナメさんは、そっか、と小さく呟いた。
15.
日記帳代わりのノートを机の上に開いて、カナメさんにもらった万年筆を手にとる。キャップの端に彫られたわたしのイニシャルを指でなぞって、それからキャップを外した。わたしは林さんとのやりとりや、カナメさんに言われた「好き」という言葉を、何度も思いかえしていた。それを今日の出来事として書きとめるべきか、悩んでもいた。
わたしはどうすればよかったのだろう。ほんとうは、カナメさんに対して言うべきことが、もっと他にあったんじゃないだろうか。
——恋愛感情。
ノートにそう書きつけて、わたしはその文字列を眺める。好きだと言われて礼を述べたわたしに、カナメさんがどこか寂しそうに微笑んだことを、思いだした。
わかりたくない。わたしはふと、そう思った。恋愛感情がいったいどういうものなのか、わたしがカナメさんに恋愛感情を抱いているのか、そんなことわかりたくない。
——わかりたくない。
わたしはそれをノートに書きたして、万年筆のキャップを閉めた。
電車の窓の外を眺めて、それからボックス席の向かいに座るホツエとシズエに目をやった。
「晴れてよかったよね」
シズエはコンビニで買ったサンドイッチを頬張りながら、そう言った。
「うん。今日はありがとうね」
ホツエはペットボトルのお茶を飲みながら笑う。
「傷心旅行とか言うけどさ、ホツエそんなに傷心してなくない?」
「えー、せっかくの旅行だから楽しまなくちゃ損じゃん! ほんとうはめちゃくちゃ傷ついてるんだから!」
そう言ってホツエは少し口を尖らせたけれど、わたしの目にもそんなに傷ついているようには見えなかった。三谷先生にはきっと断られるだろうと予感していたから、あまり傷ついていないのだろうか。それとも、本人が言うように「ほんとうはめちゃくちゃ傷ついてる」のだろうか。
「まあ、旅行というほどでもないよね、これ」
シズエが言う。わたしたちが向かっているのは、電車で三十分もかからない場所にある紅葉の名所だ。泊まる予定もなく、きっと夕方には家に戻っているだろう。
目的の駅について、わたしたちは電車を降りた。広い通りを歩いて、寺へと向かう。あたりは人で賑わっている。おそらくその大半は、わたしたちと同じように紅葉を見にきているのだろう。
「これじゃあ、紅葉じゃなくて人を見にきたみたいだね」
シズエがそう言って笑う。十分ほど歩いて着いた寺の周りは、人で溢れかえっていた。
「私たちも写真撮ってもらおうよ」
ホツエがそう言って、通りがかりの人に、写真お願いできますか、と声をかける。いいですよ、と頷くその人にホツエは携帯電話を渡し、わたしたちは一本の楓の木の前に並んだ。
「お願いしまーす」
撮影が終わり、差しだされた携帯電話を受けとるとホツエは、ありがとうございました、と元気よく言って、わたしたちはまた歩きだした。
「今度これプリントしとくね」
「よろしく」
ホツエの言葉にシズエが答える。なかば人に流されるようにして、わたしたちは寺の周りをぐるりと回った。
「あ、そこのカフェ入ってみない?ちょっと疲れたし」
シズエの言葉に頷いて、わたしたちはカフェに入った。賑わってはいるが空いている席もあり、すぐにテーブル席に通された。
「私はメロンソーダにする」
メニューを開いてすぐにシズエが言う。その手からホツエがメニューを取って、どうしようかなあ、と呟きながら眺める。
「アイスコーヒーある? あるならそれで」
わたしが言うとホツエは、あるよ、と答えた。それから少しして、口を開く。
「私もメロンソーダにしようっと」
わたしは近くにいた店員を呼んで、メロンソーダを二つとアイスコーヒーを一つ頼んだ。
店員はにっこり笑って、かしこまりました、と言い去っていく。
「ホツエってさ、恋人が欲しいっていうより、誰かのこと好きでないといられないだけなんじゃないの」
シズエがそう言うとホツエは、うーん、と首をひねった。
「そうかなあ? 恋人欲しいよ?」
ふうん、とシズエはさして興味もなさそうに頷く。
「じゃあ先生なんか好きになってないで、つきあえそうな人探せばいいのに」
「誰を好きになるかなんて選べないじゃん」
まあそれはそうだけどさあ、とシズエは呟く。
わたしはふと、恋人がいたらどんないいことがあるのだろうか、ということを考えた。そもそもなにか「いいこと」が、あるのだろうか。
「はあ、三谷先生やっぱり好きだなあ……」
ホツエがどこかうっとりしたように言葉を紡ぐ。
「振られたんでしょ、きっぱり諦めなよ」
シズエの言葉にホツエは、うう、とうめく。
誰かを好きになること——恋愛感情で好きになること——は、うっとりするほど心地よいものなのだろうか。だとしたらわたしがカナメさんに対して抱く「好き」は、恋愛感情ではないのだろうか……。
「お待たせしました」
店員がトレイの上にグラスを三つ乗せて、テーブルの傍に立った。わたしたちはそれぞれの飲み物を受けとって、ごゆっくりどうぞ、と言って去っていく店員を見送った。
「シズエは、誰かのこと、好きになったことあるの? 恋愛感情で」
「あるよ」
わたしの問いかけに、シズエは答えてメロンソーダをすする。
「それが恋愛感情だって、どうしてわかるの?」
「どうしてって……、そりゃわかるでしょ」
シズエは不思議そうな顔をしてこちらを見る。
「わたし、よくわからなくて。恋愛感情っていうのが、どういうものなのか……」
わたしはアイスコーヒーに少し口をつけて、そう言った。
「うーん、でもさ、そういうのって理屈じゃないじゃん?」
シズエの言葉にわたしは、はあ、と曖昧に頷く。
「きっとアリカも恋すればわかるって」
16.
部室にはカナメさんと川口さんがいた。カナメさんは「デクレッシェンド」を描いているキャンバスの前に立っている。川口さんは椅子に座って、机の上で水彩画を描いているようだった。
わたしは自分のキャンバスに視線を走らせて、思わず首を傾げた。「ゲシュタルト崩壊」と題した描きかけの絵の、青く塗ったはずの空が真っ白になっている。いくつもの薄い青い色で、空を塗ったはずだ。夢でも見ていたのだろうか。いや、わたしはパレットに青い絵の具と白い絵の具を出して混ぜたことも、それを少しずつキャンバスの上のほうに伸ばしたことも、はっきりと覚えている。
キャンバスの前に立って、もう一度よく見てみる。やっぱりキャンバスの上のほうには、なにも塗られていない。
「アリカちゃん、それ描きなおしてるの?」
わたしの傍へ来て、カナメさんがそう訊いた。
「ほとんどできかけてたよね?」
「はい、空を青く塗って……」
「そうそう、あの色、綺麗だったけどなあ」
やっぱり夢を見ていたわけではない。わたしは確かに空を塗ったし、カナメさんもそれを見たのだ。けれど、塗ったはずの空の色が消えているんです、と言うのはなんだかはばかられた。
「えっと……、なんとなく、自分では空の色がちょっと違うなって思って、それで描きなおしてるんです」
「ずいぶんと熱心なんですね」
川口さんがどこか刺々しい口調でそう言った。わたしは部屋の後ろの棚へと歩いていき、画材の箱を手にとる。わけがわからないけれど、消えてしまったものは仕方がない。とにかくこの絵を完成させるためには、もう一度塗りなおすしかないだろう。
油彩用のパレットの上に、青い絵の具と白い絵の具を絞りだす。そして筆に少しオイルをつけて、二つの色をかき混ぜる。そうしてできた空色を、キャンバスに広げていく。
「そういえば、川口さんも美術館のコンテスト出す?」
カナメさんの問いに川口さんは、はい、と小さく答える。
「晴野先輩は、その絵を出すんですか?」
そう言って川口さんは、カナメさんの「デクレッシェンド」が描かれたキャンバスのほうへ目を向けた。
「うん、そのつもりだよ」
「なんだか、不思議な絵ですよね。素敵です」
どこかうっとりするように、川口さんはそう言った。
「ありがとう」
わたしは二人のやりとりをよそに、ほんの少しずつ色を変えながら「ゲシュタルト崩壊」の空を塗っていく。どうして塗ったはずの空の色が消えたのだろう、とまだ考えながら。いや、考えても仕方ない。現に消えてしまっているのだから。不思議で仕方ないけれど、とにかくわたしはこの絵を完成させて、コンテストに出したい。もちろん初心者のわたしが入賞なんてできるとは思っていないけれど、それでも描いて、コンテストに出す、そのことがとても意味のあることに思えた。
今日はなにを書こうか、と考えながら抽斗を開ける。日記帳代わりのノートを取りだして、開いた。
真っ白だ。
最初のページから最後のページまで、どこにもなにも書かれていない。何度もページをめくって確かめてみたけれど、まるで買ったばかりの新品のように、真っ白で、綺麗だった。
——そんなわけ、ない。
昨日までこのノートに毎日のように日記を書いていて、もう半分くらいは使ったはずだ。まさか、誰かが取りかえたのだろうか。わたしはノートを机の上に置いて、リビングへ向かった。母がソファに座って携帯電話をいじっている。
「ねえ、わたしの日記のノート、どこかにやった?」
「日記? 日記なんか書いてたの?」
「え……、うん、そうだけど……」
母は不思議そうな声をあげて、こちらを一瞥した。どうやら母がノートを取りかえたということはないようだ。もしもわたしが訊かなければ、日記を書いていることなど知られずにすんだのか、と思うと少し恥ずかしかった。
「へえ」
それだけ言うと、母はすっと携帯電話に目を落として、またいじりはじめた。わたしはとぼとぼと自室に向かい、もう一度机の上のノートを開いてみる。やっぱり真っ白だ。わけがわからないけれど、仕方ないので机の隅に置いていた青い万年筆を手にとる。そしていつものように思わず、キャップに刻まれたわたしのイニシャルを指でなぞった。それからキャップを外し、ノートの最初のページに今日の日付を書いた。その下に、今日の出来事を箇条書きしていく。描きかけの「ゲシュタルト崩壊」の空の色が消えたこと。使いかけのノートが真っ白になっていたこと。
いったい、なにがどうなっているのだろう。わたしは自分でノートを買いかえて、その記憶を失ってしまったのだろうか。でも、「ゲシュタルト崩壊」の空の色は?カナメさんも確かに見ていたし、それを覚えていた。だから、わたしの記憶違いではない。それともわたしはほんとうにあの絵をイチから描きなおして、その記憶を失ったのだろうか。
なんだか頭が痛い。わたしは万年筆のキャップを閉めて机の上に置き、ノートを抽斗の中へしまった。
17.
部室へ入ると、ホツエとシズエがそれぞれのキャンバスに向かって筆を走らせていた。わたしは自分のキャンバスの前に立ち、それをよく見てみる。大丈夫、空の色は消えたりしていない。ただ、もう少し深みのある色にしたいと思って、部屋の後ろの棚から箱を取り、机の上に画材を並べる。絵の具のチューブの入った箱を開けて、思わず首を傾げた。なぜだろうか、青い絵の具のチューブだけ入っていない。わたしはしばらく、青い絵の具のチューブが入っていたはずの空間を見つめて、静止していた。
「どうしたの?」
こちらを振りかえって、ホツエが訊ねる。
「青い絵の具がない……。持って帰ったりとか、してないんだけど……」
「えー、誰かが間違えて持っていっちゃったとか?」
シズエもこちらを向いて、不思議そうに言った。
「間違えるかなあ……。しかも青い絵の具だけ、ないんだよ?」
わたしはそう言いながら、とりあえずパレットの上に白い絵の具と黒い絵の具を絞りだした。
「ひょっとしてイタズラだったりして。とりあえず私の貸すよ」
ホツエがそう言いながら机の前にやってくる。そして青い絵の具のチューブをわたしのほうへと差しだした。
「ありがとう」
いたずら……。こんなくだらないいたずらを、いったい誰がするというのだろう。しかも、青い絵の具だけだなんて。
わたしは青い絵の具のチューブを受けとり、パレットの上に青い絵の具を絞りだした。
「なんだろうねえ?でも、ヤエちゃんならしそうかも、とか思っちゃう」
「川口さんが?」
ホツエの言葉にわたしは訊きかえした。
「まあ、いたずらなら青だけじゃなくて全部持っていっちゃう気もするけど」
シズエがそう言うとホツエが、まあ確かに、と頷く。
「なんで川口さんならしそう、って思うの?」
わたしは二人に向かって問いかけた。
「やっぱりアリカは鈍いなあ。ヤエちゃん、晴野先輩のこと好きなんだよ、どう考えてもさ」
シズエが笑いながら答える。
「そうなの……? でもそれとこれと、どう関係があるの?」
「えー、わかんない?晴野先輩はアリカのこと好きじゃん。だから嫉妬だよ、嫉妬」
今度はホツエが笑いながら言った。確かにカナメさんはわたしのことを好きだと言ったけれど、周りから見てもそれがわかるものなのだろうか。
「カナメさん、わたしのこと好きなのかな?」
好きなのかな、もなにも、わたしは本人から好きだと言われたのだけれど、そのことを二人に打ちあけようとは、どうしてか思えなかった。
「どう考えてもそうじゃん、まさか気づいてなかったの?」
「え、いや……」
シズエの言葉に、わたしは言葉を濁し、パレットと筆を持ってキャンバスに向かった。パレットの上で青い絵の具と白い絵の具を混ぜて、そこにほんの少しだけ黒い絵の具も混ぜてみる。
「ていうかさ、アリカも晴野先輩のこと好きでしょ? 前言ってた好きな人って、晴野先輩じゃないの?」
今度はホツエが口を開いた。
「え……、まあ、好きだけど……。恋愛感情かはわからないっていうか……」
「なんかじれったいなあ」
笑いながら言うシズエの言葉に、いつか林さんに言われた「曖昧な態度」という言葉を思いだす。
——好き。
わたしは筆をキャンバスに軽く叩きつけながら、何度も「好き」という言葉を頭の中で繰りかえした。繰りかえせば繰りかえすほどに、わけがわからなくなる。
とにかくこの絵を完成させよう。軽くかぶりを振って、わたしはキャンバスに空の色を広げていった。
抽斗からノート——半分くらいは使っていたはずなのに、真っ白になってしまっていたあのノート——を取りだし、机の上に開く。万年筆を取ろうと手をのばして、いつもそこに置いていた万年筆がないことに気づいた。
カナメさんにもらった青い万年筆が、ない。机から転がり落ちてしまったのだろうか。机の下を見ても、念のためにベッドの下を見ても、万年筆はなかった
なくすのが怖くて、どこにも持ちださないようにしていたのに。抽斗を開けても、手前の隅に包装された箱があるだけだ。
仕方なく、ボールペンを手にとってノートを開き、「万年筆が行方不明」と書きつけた。そして自分の書いたその文字列を見て、なんだか馬鹿馬鹿しくなった。わたしはボールペンをノートの上に置いて、椅子の背もたれに体重を預ける。それから思いっきり、わざとらしいくらいに——誰に見られているわけでもないのに——思いっきり、背伸びをした。
はあ……。
口には出さずに、溜息をつく。背もたれから背中を離して、もう一度ボールペンを手にとる。そしてノートにぐるぐると不恰好な円をいくつも描いた。
——ごめんなさい。
とてもじゃないが、プレゼントでもらった万年筆をなくしてしまいました、なんてカナメさんには言えない、言いたくない。だからせめて、とわたしは謝罪の言葉をノートに書いた。そしてしばらくぼんやりしてから、その下に「好きです」と書きくわえた。
これは、恋愛感情というものなのだろうか。
どうすればわかるのだろう。そもそも、わかる必要があるのだろうか。わたしはノートを閉じて抽斗の中に入れ、部屋の明かりを落としてベッドに身を横たえた。布団を頭まで被って、目を閉じる。なにも考えない、なにも考えない……。一所懸命にそう頭の中で呟いても、脳裏にはカナメさんの優しい微笑みが浮かんでくる。一刻もはやく意識を手放したいのに。
——僕はね、君が好きなんだ。
カナメさんの声が、わたしの耳朶によみがえる。やっぱりわたしはあのとき、なにかもっと言うべきことがあったのではないだろうか。
いや……。
なにもない、なにもない。わたしは声に出さずにそう呟く。瞼に力を込めて、とにかく眠ろうとした。どうか夢に出てこないで。そんなことを考えながら。
18.
「なんで私たち、こんなに左に寄ってるんだろう?」
食堂のテーブルの上に、ホツエとシズエが並んで写った写真がある。それは、ホツエの傷心旅行と銘打って紅葉を見にいったときに、通りがかりの見知らぬ人に撮ってもらった写真だった。確かに二人は左のほうに寄って写っていた。
「というかさ、これアリカも一緒に、三人で並んで撮ってもらったよね?」
「でもアリカ写ってないよ?」
シズエの言葉に、ホツエは不思議そうに首を傾げる。
「わたしも、一緒に撮ってもらった記憶があるけど……」
おずおずとそう言っては見たものの、写真にはやっぱりホツエとシズエしか写っていない。ホツエは、うーん、と困った顔で唸る。
「なんなんだろうねえ」
シズエはそう言って、コップを口につけた。わたしは二人が写っている写真を眺めているうちに、なんだか胸がざわざわしてきた。食器の乗ったトレイを手に、立ちあがる。
「わたし、行くね。次の時間は講義ないから、部室に顔出してみる」
ホツエが、行ってらっしゃい、と言うのを背に聞きながら、わたしは部室へと向かった。
部室にはカナメさんと川口さんがいた。それぞれ自分のキャンバスに向かって、筆を走らせている。わたしが、こんにちは、と声をかけると、カナメさんがそれに答えてくれた。けれど、川口さんはこちらを見ようともしない。
「コンテストの絵、もうだいぶできたかな?」
「そうですね、そろそろ完成にしようと思います。細かいところはいろいろと気になるけど、気にしすぎると終わりそうにないですし」
カナメさんの問いに答えて、わたしは部屋の後ろにある棚から箱をひとつ取りだす。そして机の上に画材を並べた。絵の具のチューブの箱を開けてみると、やはり青い絵の具はなく、しかも白い絵の具までなくなっていた。
「あの、カナメさん、青い絵の具と白い絵の具、貸してもらえませんか?」
「いいよ。でも、どうしたの?」
わたしは問われて、一瞬言葉に詰まる。
「えっと、使い切っちゃったので……」
「そんなに青と白が好きなんですか」
適当な嘘をつくわたしに、川口さんがどこか馬鹿にするようにそう言った。そういえば川口さんは、いまだにわたしに敬語を使っている。
「はい、どうぞ」
カナメさんが差しだした青と白の絵の具のチューブを受けとり、パレットの上に絞りだす。そして二つの色を混ぜて、筆ですくいとった。既に青く塗った空に、また少しだけ色味の違う空の色を重ねていく。
ふと川口さんのほうへ目をやると、どこか乱暴な手つきで筆を走らせていた。
「なんですか」
キャンバスのほうを向いたまま、川口さんが声を発する。
「いや……、綺麗な絵だなって思って」
「お世辞とかいりません」
わたしの言葉に、川口さんはぴしゃりと言った。
「お世辞のつもりじゃ、ないんだけど……」
川口さんはわたしの言葉を無視して、筆でときどきパレットから絵の具をすくいとり、またキャンバスに走らせる。わたしは自分のキャンバスに向きなおり、ぼんやりと自分の描いてきた「ゲシュタルト崩壊」を眺める。青い空に、崩れてゆくビル群。まだ手直ししたいところはあったけれど、ひとまずこれで完成ということにしよう。わたしは青い絵の具と白い絵の具をカナメさんに渡した。
「ありがとうございました。わたし、今日は帰りますね」
「うん、お疲れ。気をつけて帰ってね」
わたしは頷いて、荷物をまとめ、部室を後にした。
教室の後ろのほうの席について、鞄を開ける。ノートとペンケースを取りだして、解析入門のテキストが見当たらないことに気づいた。
「おはよ」
振りかえるとホツエがにこにこしながら、わたしの後ろの席に座るところだった。
「どうしよう、テキストがない」
「じゃあ私の見せようか?」
ホツエはそう言って立ちあがり、わたしの隣の席へと移動する。
「ありがとう。でも、絶対に鞄に入れてきたんだけどな……」
「寝ぼけてたんじゃない?」
そう言ってホツエは笑い、解析入門のテキストをわたしにも見えるように開いて置いた。
「うーん……。それにしても今日は遅刻しなかったんだね、珍しい」
「最近はちゃんと遅刻しないように来てるよ」
「三谷先生が好きだから?」
わたしがそう問いかけると、ホツエは少し顔を赤らめた。
「いやいや、振られちゃったもん」
そう言いながらもホツエは、どことなく嬉しそうに見えた。
「そのテキストって、どこで買えるかな?」
わたしはテキストを指さして訊ねる。
「さあ……? 三谷先生に訊いてみたら?」
「そうだね。後で行ってみる」
ホツエは、うんうん、と頷く。
少しして、三谷先生が教室に入ってきた。そして、おはようございます、と言ってから、わたしのほうを見て怪訝そうな顔をした。けれどそれ以上なにを言うわけでもなく、チョークを手にとって黒板に数式を書きはじめた。
「前回やったことはさすがに覚えているでしょう」
黒板にチョークを滑らせながら、三谷先生が言う。この人は前回やったことどころか、これまで見聞きしたものすべてを覚えているのだ、と思うと、やっぱり不思議に思えた。忘れることができない……。それはいったい、どんな感じなのだろう。
そしてわたしは、これまでにどれだけのことを、忘れてきたのだろう。きっと忘れたほうがいいことも、その中にはたくさんあったのだろうけれど、忘れたことすらも忘れているのだと思うと、少しぞっとした。
「どうぞ」
扉をノックすると、向こう側から三谷先生のくぐもった声が聞こえてきた。わたしは扉を開けて、研究室へと足を踏みだす。
「どちらさまかな。今日の僕の解析入門の講義にも、いましたよね」
「え?」
三谷先生が眉をひそめてそう言ったので、わたしは思わず裏返った声を出してしまった。
「あの……、解析入門の講義を取っている東雲アリカですが……。テキストをなくしてしまったので、そのことで……」
「あなたの顔は初めて見ましたよ。今更、あの講義に初めて来たんですか?」
しどろもどろに言葉を紡ぐわたしを、三谷先生は睨みつけるようにして咎める。
「ちょっと待ってください。今までもずっと講義には出ていました」
「そんなわけありません」
「どうして、そんなこと……、言いきれるんですか? まさか……、まさか、講義に来ている学生全員の顔を覚えている、とでも……、仰るんですか」
それを言っていいのか悪いのか、わからないながらも言わずにいられなかった。つっかえながらもなんとか言葉を搾りだす。三谷先生は眉を少しだけしかめて、わたしの目をじっと見た。負けじとその目を見返す。むしろ睨みつけるような心持ちで。
沈黙。お互いにただ見つめあって、何も喋らない。さすがにもう、耐えられなくなってなんとか口を開いた。
「先生は……、一度見たものや聞いたものは、決して……、忘れないんですよね?」
三谷先生が目を見ひらく。
「なぜそれを知っているんですか……?」
心底びっくりしたように、そしてどこか恐ろしげな表情で、そう問いかけられた。
「先生が教えてくれたからですよ。わたしと……、白崎ホツエっていう子に」
「白崎さんは知っています。でも、あなたの顔は今日初めて見ましたよ」
そんなわけ、そんなわけない……。いったい、どういうことだろう。わたしはわけがわからず、途方に暮れた。三谷先生の顔がだんだんと、冷たい真顔へと変わっていった。
「ああ……、なるほど……」
独り言のように呟いて、頷く。
「僕をからかいに来たんですね。確かに白崎さんには、僕が一度見たものや聞いたものを決して忘れない、ということを話しました。あなたは白崎さんからそれを聞いて、僕をからかいに来た。……違いますか?」
三谷先生は語気を強めながら、そう言い、こちらを睨みつけた。
「先生こそわたしをからかってるんじゃないんですか? だって、わたしもホツエと一緒にここに来て、先生が一度見たものや聞いたものを決して忘れない、ってことを聞いたんですから。絶対に、聞きました。絶対に……!」
わたしは声を張りあげて、まくしたてるように言い返す。けれど三谷先生はやっぱりわたしを睨みつけている。
「僕の記憶が間違っているはずがないんですよ。それに、いい大人が学生をからかって、どうするっていうんですか」
……そうだ。三谷先生の記憶が間違っているはずはない。それなら、わたしの記憶が間違っているのだろうか。わたしは決して記憶力がいいわけではない。
だんだんと自分の記憶に自信がなくなっていく。ホツエがこの部屋へ来たとき、わたしも一緒にいた……、それはわたしが作りだした偽の記憶なのだろうか。そしてわたしは、さっき三谷先生が言ったように、ホツエからその話を聞いただけなのだろうか。
いや……、そんなわけ、ない。けれど三谷先生は現に、わたしのことを覚えていない。
「先生は……、ほんとうに、絶対に……、忘れないんですか?」
そう訊ねるわたしの声は、もはや力を失っていた。
「そうですよ。白崎さんに聞いたんでしょう」
――違う、あなたから直接聞いたのだ。
そう言いたかったけれど、わたしの口は動いてくれなかった。
「東雲さんと言いましたね。くだらないことはやめて、帰ってくれませんか。テキストなら、学内の書店に……」
「あの、ほんとうに申し訳ありませんでした……!」
三谷先生が言いおえないうちに、わたしは叫ぶようにそう言って、研究室から飛びだした。
19.
わたしの絵がない。ほぼ完成していた、あの「ゲシュタルト崩壊」が、ない。わたしのキャンバスがあったところにはなにもなく、ぽっかりとただ空白がある。
「あの……、わたしのキャンバスが、ないです……」
キャンバスに筆を走らせるカナメさんに向かって、わたしは呟くようにそう訴えた。
「昨日までそこにあったよね?」
「はい。持って帰ったりは、してないんですけど……」
カナメさんは首を傾げる。
「誰も、他人のキャンバスを勝手に動かしたりは、しないと思うんだけど……」
「そうですよね……」
わたしはそう答えたけれど、現にわたしのキャンバスは、見当たらない。
「どうせ自分で隠したんでしょ? かまってちゃんって、ほんとイヤ」
川口さんが刺々しい声でそう言った。
「やめなよ、川口さん……、そういうこと言うのは……」
「先輩ってほんとに東雲さんに甘いですよね」
たしなめるカナメさんに、川口さんはそう答えて、手に持っていた筆を机の上に放りなげる。そしてそのまま、鞄を掴んでばたばたと部屋を出ていった。
「気にしちゃダメだよ? 僕は、君が自分でキャンバスを隠したなんて、思ってないから」
少しの気まずい沈黙を、カナメさんの柔らかい声が破った。
「私もだよ。でも、どこに行っちゃったんだろうね?」
続いて、佐々木さんがそう言う。あんなに大きなキャンバスが、イーゼルごとどこかに行ってしまうなんて、ありうるのだろうか。美術館のコンテストに出すつもりで、もうほとんどできあがっていたのに。また最初から描きなおすのか、あるいは別の絵を描くのか。どちらにせよ、気が遠くなる話だった。
「もしかしてさあ……」
林さんが口を開く。
「川口さんが、隠したんじゃねえの?」
「川口さんが……?」
林さんの憶測に、カナメさんが訊きかえす。
「そう。キャンバスを『隠す』だなんて、自分がやったから、そんな言い方したんじゃねえのかな、って」
「でも、なんでそんなこと?」
「東雲さんのこと、嫌いだからだろ」
カナメさんの問いに、林さんはにべもなく答えた。
「わたし、川口さんに嫌われてるんですか?」
思わずわたしは、林さんに向かってそう口にした。
「自覚ねえのかよ。どう考えても嫌われてるだろ。さっきだって、かまってちゃんだとか言ってたし。今までだってあの子、よくあんたを睨みつけてたし」
林さんは、どこか呆れたようにそう言った。
「わたし、嫌われるようなこと、しましたかね……?」
わたしがそう呟くと、林さんは少し口ごもって、それからまた口を開いた。
「まあ、東雲さんがどうこうというよりは、カナメのせいだな」
「え、僕?」
カナメさんはびっくりしたように、裏返った声をあげる。
「いや、カナメのせいって言うのも変か……。要するに嫉妬だろ。カナメと東雲さんが仲良いのが、気に食わないんだろ」
「そんなに違うかなあ? アリカちゃんにも川口さんにも、同じように接してるつもりだけど……」
「ほら、それだよ。まず呼び方が違うじゃねえか」
呆れかえったように指摘する林さんに、カナメさんはバツの悪そうな顔をして黙りこんだ。
「それにな、お前は東雲さんへの、好きって気持ちを、全然隠しきれてねえんだよ」
「え、そ、そう……?」
林さんの更なる指摘に、カナメさんは少し顔を赤くして焦ったような表情を見せる。
「じゃあ、さっき言ってた、嫉妬、って……」
わたしはおずおずと口を挟んだ。
「川口さんもカナメのことが好きなんだよ」
納得しかけてから、わたしは違和感に気づいて口を開いた。
「川口さん『も』って、どういうことですか」
「どういうことって……、それはあんたが一番よくわかってるだろ。あんたも、カナメが好きだ、って」
「いや、だから、好きですけど、それは人として好きということであって……」
「はいはい、わかったわかった」
林さんはあしらうように、わたしの言葉を遮った。
「でも、いくらなんでもそこまでするかな?キャンバス動かすの大変だし、隠せるような場所もそうそうないでしょ?」
「まあ、それもそうだけど……」
ふいに口を開いた佐々木さんに、林さんは歯切れ悪く答えた。そしてしばらく、わたしたちは黙りこんだ。林さんは自分のキャンバスに向かって筆を走らせ、佐々木さんは考えこむように首を動かしていた。カナメさんは自分のキャンバスの前で俯いている。
「描きなおします。コンテストに出すつもりでしたし」
わたしはそう言って、部屋の後ろに並んだいくつかのイーゼルの中から一つを持ちあげて、昨日までわたしのキャンバスがあった空間へとそれを運んだ。それからまた部屋の後ろに行き、数枚積まれた新しいキャンバスから一枚を引きだして、イーゼルに立てかけた。真っ白なキャンバスを改めて眺めると、思わず溜息をついてしまう。どう考えても間にあわない。あの絵を描くのに、わたしはどれだけ時間を使っただろうか。実際に筆を動かしていた時間は計っていないけれど、今からコンテストの締切までに同じ絵を描くことなど、できるのだろうか。
「無理すんなよ。そりゃ、せっかく描いてた絵がなくなって、悔しいのはわかるが……」
「べつに、悔しいわけじゃないですけど」
わたしを気遣うような林さんの声に、思わずそれをはねのけるような言葉を返してしまった。口をつぐんだ林さんに謝ろうかと思ったけれど、思いなおして画材を机の上に並べる。パレットに白い絵の具と黒い絵の具を出して、オイルで濡らした筆でその二つの色を混ぜた。まずは灰色のビル群。大丈夫、一度描いたものをもう一度描くだけだ。一度目よりは短い時間でできあがるはずだ。
わたしが無心でキャンバスに向かっている間に、佐々木さんが帰り、林さんが帰り、そしてカナメさんも帰ってしまった。カナメさんは、鍵を事務所に預けるのを忘れないでね、と言って名残惜しそうに部屋を出ていった。窓の外には夜が広がっていて、部屋の中まで少し寒くなっている。
わたしは手をとめて、わたしのことを「かまってちゃん」と言った、川口さんの刺々しい声を思いかえした。そして、くだらない、と頭の中で呟く。もう一度、くだらない、と呟く。
くだらない。くだらない。くだらない。
20.
部室には川口さんしかいなかった。わたしはよっぽど、開けたばかりの扉を閉めて家に帰ってしまおうかと思った。けれど、少しためらっている間に川口さんがこちらに目をやったので、引くに引けなくなってしまう。川口さんはどこか、いつもと雰囲気が違うような気がした。少し不思議そうな顔でわたしを見ている。
仕方ない。
「こんにちは」
わたしははっきりとそう声に出しながら、部室の中へと足を踏みいれる。それから窓際に並ぶキャンバスに目をやり、描きなおしている「ゲシュタルト崩壊」の絵がちゃんとあることを確認した。
「えっと……、こんにちは。どなたですか?」
ただただ不思議そうにそう訊ねる川口さんに、わたしは言葉を失った。しっかりと川口さんの目を覗きこんでみたけれど、ほんとうにわたしが誰なのかわからないようだった。そもそもこれがいたずらの一環だとしたら、あまりにもくだらなすぎる。
「あー、新入部員の東雲って言います……」
「そうなんですね。私は川口です。よろしくお願いします」
働かない頭で捻りだしたわたしの嘘に、川口さんは丁寧に答えた。そしてキャンバスへ向きなおり、筆を動かしはじめる。
「えっと……、カナメさん、いや、あの、晴野先輩に、ここに来るように言われたんですけど……」
「晴野先輩なら、さっき帰りましたよ? 晴野先輩のお友達なんですか?」
嘘を重ねるわたしに、川口さんは訝しげに訊ねる。わたしは心の中で、ああ……、と情けなく唸った。そして、もう一度ない頭をひねる。
「今日じゃなくて明日だったかも……。えっと、じゃあわたし、帰りますね……」
「そうですか。お疲れさまです」
——晴野先輩のお友達なんですか?
わたしはそれに答えなかった、と心の中で呟きながら、部室を飛びだすような気持ちで扉の外へ出た。
おかしい。絶対に、おかしい。
廊下を歩きながら、頭の中でそう繰りかえす。三谷先生に忘れられ、川口さんにも忘れられた。いったい、そんなことがありうるだろうか。
それとも……。わたしは大掛かりないたずらでも仕掛けられている?
いや、三谷先生と川口さんには、おそらく接点がない。仮にあったとして、大学の教員と学生が手を組んで、こんな馬鹿げたことをするわけがない。
わたしが、おかしいのだろうか。わたしの記憶が、間違っている? 三谷先生とも川口さんとも、わたしは初対面なのに、わたしが二人との架空の記憶を作りあげて……。
いやいや、とわたしは頭を振った。
「ねえ、わたしって、おかしい?」
食卓でわたしは母に向かって訊ねる。
「はあ?」
母は不思議そうな声をあげて、わたしの目を見つめた。わたしはそれを真っすぐ見つめかえして、もう一度口を開く。
「わたしって、おかしい?」
「おかしい、ってなによ」
首を傾げながら母が訊ねる。
「頭が……、その、おかしいというか」
「ほんとうに頭がおかしい人は、自分がおかしいんじゃないか、なんて思わないでしょ」
わたしの言葉に、母はどこか呆れたようにそう言った。
「そもそも、頭がおかしいって、なに。おかしいもおかしくないもないでしょ。誰かにとっておかしいものは、別の誰かにとってはおかしくないでしょ」
思わずわたしは、ううん、と唸る。
̶̶あのね、わたしのこと、忘れられちゃったの。しかも、二人から。一人は一度見聞きしたものは絶対に忘れない人で、それなのにわたしのこと忘れてたの。
そこまで言うことを考えて、けれどわたしはなにも言えなかった。だって、やっぱりおかしいとしか、思えなかったから。わたしを忘れたあの二人がおかしいのか、それともわたしがおかしいのか、それはわからない。いや、もうなにもかもが、世界のすべてが、おかしく思えた。
「この前、万年筆がどうとか言ってたでしょ。ちょっと疲れてるんじゃない? 最近は帰りも遅い日が多いし。そんなに勉強ばっかりしなくてもいいの。お父さんの言うことなんて気にしなくていいから」
わたしはコップに麦茶を注いで一気にあおった。そういえばわたしは、美術サークルに所属したことを母に言っていない。母はどうやら、わたしが遅くまで大学に残って勉学に励んでいると思っているようだ。
父の顔がふと脳裏をよぎる。最近は以前にも増して顔を合わせることがなくなった。父はとにかく忙しいらしく、朝はやくから夜遅くまで働いているようだった。休日もほとんど家にいない。
「お父さんこそ、働きすぎなんじゃないの」
わたしは思わずそんなことを口走って、それから後悔した。けれど母は曖昧に微笑んでみせる。
「あの人は好きで働いてるの。ワーカホリックってやつ。ああいうのは、自分が倒れてやっと気づくもんなの」
「心配じゃないの? だって、ほんとうに倒れちゃうかもしれないんだよ?」
どこか達観したような母の言葉に、わたしは思わず食ってかかる。母は、そりゃあねえ、と少し間延びした声を出した。
「心配は心配。でもしょうがないでしょ。こっちからはどうしようもないんだから」
21.
部室の扉を開けると、林さんと佐々木さんがそれぞれキャンバスに向かって筆を走らせていた。
「こんにちは」
「やっほー」
二人に向かって挨拶しながら部屋へ入ると、佐々木さんが明るく声をかけてくれた。
「ん? 新入部員?」
「え?」
こちらを向いた林さんの言葉に、わたしの声は裏返った。
「林くんがジョーク言うなんて珍しい」
佐々木さんがそう言って、ほんとうにおかしそうに笑い声をあげた。わたしは一瞬ほっとしたけれど、林さんの怪訝そうな表情を見て、また不安になる。
「いや……、え、誰……?」
「ちょっと、ほんとに言ってるの? アリカちゃんじゃん、東雲アリカちゃん!」
佐々木さんは笑うのをやめて、真剣な顔つきで林さんに詰めよる。林さんは困ったような顔でこちらを見ていた。
「そ、そうだっけ……。悪い、俺、人の顔覚えるの苦手で」
「ええ……」
佐々木さんも困り顔になって、こちらを向いた。わたしは思わず、首を傾げてみせた。
「じゃあ、あんたは俺のこと知ってんの?」
「林ユウさん、ですよね……」
「ああ……、そうだけど……」
林さんはますます困ったような顔をした。
「と、とりあえず、もう忘れちゃダメだよ!」
場を取りなすように佐々木さんが言った。林さんは低い声で、ああ、と答える。
嘘だ。
けれど目の前にいるのは、ただただ心の底から困ったような顔をしている林さんだった。三谷先生に忘れられ、川口さんに忘れられ、林さんにまで忘れられた。そんなこと……。
わたしは窓際に並ぶキャンバスに目をやる。ある。わたしの描きなおしている「ゲシュタルト崩壊」は、ちゃんとある。ある、ある、ある……。ふらふらとそのキャンバスの前へ歩く。そしてじっとその絵を見つめる。これはわたしが描いたものだ。
「これは、誰の絵ですか?」
わたしは林さんに向かって声を投げる。
「いや、知らねえけど……」
「わたしの絵です」
歯切れ悪く答える林さんに、わたしはぴしゃりとそう言った。
「このサークルの部員、そんなに多くないですよね。甲斐ケントさん、晴野カナメさん、林ユウさん、佐々木カンナさん、川口ヤエさん、そしてホツエとシズエ、それからわたし。まともに活動してるのはそれだけのはずです。あってますか」
わたしは自分のキャンバスに顔を向けたまま、淡々と喋った。
「そ、そうだよ……」
佐々木さんが少し怖気づいているような声で答える。
川口さん。そうだ、川口さんと林さんは接点がある……。
「林さん、もしかして川口さんと口裏でもあわせてるんですか」
「はあ……?」
わたしの問いに林さんが間抜けな声をあげる。わたしはまだキャンバスを見ながら、口を開いた。
「この間、川口さんに、忘れられてたんですよ、わたし。ついこの間……。そんなこと、ありえます?」
「知らねえよ、俺はあの子のこと正直苦手だし……。そもそも二人であんたを忘れたフリなんかして、なんの得があるんだよ」
苛立ちを隠せていない声で林さんがそう訊ねる。
̶̶俺はお前が好きなんだよ、カナメ。
わたしはいつか林さんがカナメさんに言った台詞を思いだした。そして、その林さんが言っていたもう一つの台詞も。
̶̶川口さんもカナメのことが好きなんだよ。
そうだ……。二人ともカナメさんのことを好きで、そしてカナメさんはわたしのことを好きだと言っていた。
「嫉妬ですか。カナメさんがわたしを好きだから、嫉妬してるんですか」
キャンバスから目を離し、林さんの顔を見ながらわたしはそう言った。なにを言っているんだわたしは。心のどこかでそう思いながら、それでも言わずにはいられなかった。
「佐々木さんは、覚えてますよね。わたしのキャンバスがなくなって、林さんが言ってたこと……。川口さんが隠したんじゃないかって」
林さんに顔を向けたまま佐々木さんに向かって問いかける。
「覚えてる……。でもそれは、川口さんが晴野君のこと好きだからだよね……?」
佐々木さんはおずおずとそう口にした。
「林さんも、カナメさんのこと好きなんです。そうですよね?」
わたしの言葉に、林さんはかぶりを振る。
「わけわかんねえこと……」
「わたしは、林さんから直接、聞いたんですよ」
「初対面なのにそんなことあるわけないだろ!」
林さんの言葉を遮ってわたしがそう言うと、林さんは声を荒げてわたしを睨みつけた。視界の端で、佐々木さんがあたふたと、林さんへわたしへ交互に視線をさまよわせている。
「お前らこそ、俺をからかってるんじゃねえのか?」
今度は林さんが、佐々木さんへと疑いの目を向けた。
「ち、違うよ……! それこそ私になんの得もないじゃん!」
佐々木さんは慌てて反論する。けれど、その声は弱々しかった。林さんは大きく舌打ちをした。
おかしい。おかしいのは、誰なのだろう。わたしがおかしいことにすれば、合点がいかないわけではない。わたしが偽の記憶をでっちあげて、一人で騒いでいる……。
いや、それはない。現に佐々木さんはわたしのことをちゃんと知っているし、この間わたしのキャンバスがなくなったことも知っている。それともわたしは以前に佐々木さんと口裏をあわせていて、そのことを忘れている?
わけがわからない……。
「あんた、なにがしたいんだよ」
いっそう低い声で林さんが言った。林さんこそなにがしたいんですか、と言おうかと思ったけれど、やめた。わたしは頭の中で、落ちつけ、と何度か呟く。林さんはまた大きく舌打ちをした。そして机に歩みより、画材を箱の中へ乱雑に投げいれる。
「ふざけんなよ」
小さくそう吐きすてて、林さんは部屋を出ていった。扉が大きな音を立てて閉まる。残された佐々木さんとわたしは、しばらく黙っていた。
「どうなってるの……?」
佐々木さんが沈黙に耐えきれない、とでもいうようにぼんやり呟く。わたしは、それはこっちの台詞です、と言ってやりたかった。けれどただ黙って、目を閉じる。
「アリカちゃん……?」
不安そうに佐々木さんがわたしを呼ぶ。わたしは目を開いて、佐々木さんの顔を見る。そしてなるべく自然に見えるようにと意識しながら、微笑んでみせる。
「大丈夫です、佐々木さんは気にしないでください」
自分で言いながら、いったいなにが大丈夫なんだ、と思う。きっと佐々木さんも思っただろう。けれど、佐々木さんはなにも言わずにわたしの顔から目をそらす。
「すみません。わたし、帰ります。お疲れさまです」
わたしはそう呟いて、佐々木さんを部屋に残して扉の外へ出ていった。
廊下を歩きながら、おかしい、と何度も胸の中で呟く。おかしい、おかしい、おかしい。こんなこと、ありえない。けれど、現にわたしは三人もの人間の記憶から消えている。わたしの脳裏にカナメさんの優しい微笑みが浮かびあがる。
カナメさん。
胸がざわついて仕方なかった。思わずポケットから携帯電話を取りだして、連絡先の一覧を画面に表示させる。連絡をとる相手がほとんどいないから、スクロールしなくても「晴野カナメ」という名前が下のほうに表示されている。その名前に触れようとして、やっぱりやめた。
改めて連絡先を上から眺めていく。
——覚えている。この人を、わたしは覚えている。じゃあ、この人はわたしを覚えている?
一人一人の名前を心の中で読みあげながら、わたしはそんなことをぶつぶつと、声には出さずに繰りかえした。父と母。ホツエとシズエ。高校生のときに連絡先を交換したものの、一度も連絡を取っていない数人の知りあい。それから、カナメさん。
ふと、わたしは一番上に表示されている「上島スズナ」という名前に触れてみた。そして、電話をかけてみた。
「はい……?」
数コール鳴ってから通話が始まり、電話の向こうから不審そうな声が聞こえてきた。
「急にごめん。わたしのこと、覚えてる? 高校のときに同じクラスだった、東雲アリカだけど」
なるべく静かに、けれどはっきり……、そんなことを考えながらわたしは問いかけた。
「あの……、人違いじゃないですか……?」
̶̶あなたは上島スズナさんですよね。わたしはあなたのことを覚えているんですよ。
わたしが頭にぱっと浮かんだことを口にするよりも、通話が途切れるほうが早かった。
——いや、わたしは目立つ生徒じゃなかったから……。
自分に、あるいは上島さんに、はたまたそれ以外の誰かに、言い訳でもしているような気持ちになった。
22.
部屋の扉がノックされたので、はい、と答える。扉が開いて、父が半歩部屋の中へ踏みだす。
「お前、大丈夫か?」
ベッドの上で上半身だけを起こしてぼんやりしているわたしに、父はそう訊ねた。父と土曜日に顔をあわせたのなんて、どれくらいぶりだろうか。
「お父さん、今日休みなの? 珍しいね」
言ってからわたしは、言わないほうがよかっただろうか、と考える。でも、もう言ってしまった。
「母さんから聞いた……。俺が働きすぎだって、お前が言ったんだろ?」
わたしは、ああ……、と頷く。
「大学でなにかあったのか? なんでも相談してくれていいんだぞ」
なにを今更……。そう思ったけれど、さすがにそれは口にしなかった。父とはほとんど顔をあわせないが、それが不満というわけでもなかった。正直、どうでもよかった。
——みんなが、わたしのこと、どんどん忘れていくの。
頭の中でそんな文章を組みたてて、思わず溜息をついてしまった。父はわたしの部屋と廊下の間で佇んでいる。部屋に完全に足を踏みいれていいものか、わからないのだろう。
「なにもない……。ちょっと、疲れてるだけ」
「最近、帰りが遅いって母さんが言ってたけど、その……、俺が悪かった。お前を追いつめるために、勉強しろ、って言ってたわけじゃないんだ」
はあ……。わたしはかぶりを振って、口を開く。
「べつに勉強してるわけじゃないよ。サークルに入ったの。サークルの活動に参加してるだけだから」
「サークル? なんのサークルだ?」
「美術サークル。絵を描いてるの」
父は不思議そうな顔をした。
「お前、絵を描くのが好きなのか?」
「うん、まあ……」
そうか、と父は呟いて、しばらく目を伏せた。
——もういいからほっといてよ。
もしもわたしがそう言ったら、父はどんな顔をするだろうか。父は顔をあげた。
「明日、母さんも一緒に、三人でどこか行くか?」
「なんで」
父はまた目を伏せて、いや……、と小さく呟く。
「仕事が好きなら仕事に行けば?」
「悪かった、ほんとうに。お前に心配かけてるなんて、思ってなかったんだ」
——べつに心配なんてしてないけど。
また声には出さずに、わたしは父に向かって言葉を投げる。もちろん、声に出さないから、伝わらないだろうけれど。
「わたし、明日は友達と遊びに行く予定だから」
「そうか……」
その場しのぎで適当についた嘘を、父はあっさりと信じる。言ってしまったからには仕方ない、明日は一人で図書館にでも行こうか、それともホツエやシズエに声をかけて、ほんとうに「友達と遊びに行く」のもいいかもしれない。
「その……、なにかあったらいつでも相談してくれ」
——相談しようにも、ほとんど家にいないじゃん。
そんなことを言うかわりにわたしは、うん、ありがとう、と呟いた。父は少しだけほっとしたように頷く。そして、身を向こうへと退いて扉を静かに閉めた。
林さんに忘れられてから、しばらく部室には来ていなかった。わたしは部室の扉の前で立ちどまり、ふっと息をつく。扉を開くと、部室にはカナメさんと佐々木さんがいた。林さんがいないことに、わたしは少し安堵する。
「こんにちは」
わたしが二人に向かってそう声をかけると、佐々木さんがこちらを振りかえって目を輝かせた。
「おお、見ない顔だ。もしかして入部希望者さん?」
どうして……。
「佐々木さんまで、忘れちゃったんですか、わたしのこと……」
「え?」
わたしがもはや力を失った声で問いかけると、佐々木さんは立ちどまって首を傾げた。
「わたしです、一回生の東雲アリカですよ……」
「そうだよ、今年の夏に入部した子だし、佐々木さんはアリカちゃんのことかわいがってたじゃないか」
カナメさんが佐々木さんに向かってそう言った。
「え、あれ……。ご、ごめんね……!」
佐々木さんは、わけがわからない、というような顔をしながらも、わたしに向かって慌てて軽く頭を下げる。
「ご、ごめん、私帰るね……!」
カナメさんへと、半ば叫ぶようにそう言って、佐々木さんはばたばたと画材を片付けはじめた。カナメさんは不安そうにわたしの顔を見る。わたしは小さく首を左右に振った。佐々木さんは一刻もはやく、というように部室を出ていった。
「どういうことなんでしょうか……。この前は……、川口さんにも、林さんにも、わたし、忘れられてた……」
「え?」
カナメさんは目をみはる。わたしはよっぽど、三谷先生のことも話そうかと思った。けれど、思いなおす。言ってもますます困らせてしまうだけだろうから。窓際に並ぶキャンバスに目を走らせて、ある、と胸の中で呟く。描きかけの「ゲシュタルト崩壊」は、ちゃんと、ある。わたしはそのキャンバスの前へ歩いていった。
「これ、わたしの絵ですよね……」
そう訊ねるわたしの声は、震えていた。
「そ、そうだよ? どうしたの……?」
「いえ……」
わたしは小さく首を左右に振った。どうしたの……? どうしたの、どうしたの、どうしたの……?
——どうかしている。
「アリカちゃん……」
なんだか痛そうな声で、カナメさんがわたしを呼ぶ。どうかしているのは、三谷先生や川口さん、そして林さんや佐々木さんだろうか。それとも、カナメさんやわたしだろうか。
「ごめんなさい」
なぜかわたしの口をついて出たのは、謝罪の言葉だった。
「なにを謝ってるのさ」
わからない。
「わたしが、おかしいのかもしれなくて。そうだったら、全部説明がつくし……」
「もしそうだったら、僕もおかしい、ってこと?」
わたしは力なく首を振った。
「ごめんなさい……、そんな、つもりじゃ」
「わかってるよ。僕こそ、ごめんね」
わたしたちはしばらく黙ったまま、お互いの視線を絡ませていた。いつもよりずっとはやく日が落ちていくような気がした。なにを言えばいいのか、あるいは言わなければいいのか、まったくわからなかった。
23.
手ぶらで、学食の中を歩く。いつものテーブルには、ホツエとシズエがもう座っていて、なにか談笑しているようだった。わたしは二人の向かいに腰をおろす。二人の前にはそれぞれトレイがあり、その上に空っぽになった皿が数枚ずつ、乗っていた。改めて、食欲がない、と声には出さずに呟く。ホツエが怪訝そうにこちらを向いた。
「あの……、他の席、空いてますけど……?」
なにか叫んで——あるいは、なにも叫ばずに——わたしはその場から走って逃げた。途中で振りかえって、誰も追いかけてこないことに安堵し、そして落胆した。
キャンパスを出て、駅から電車に乗る。家の最寄り駅で降りて、家に向かう。
「ただいま」
わたしは家の玄関を開けてそう言った。ばたばたと足音がして、母が玄関まで出てきた。
「どちらさまですか?」
「え……?」
母は険しい顔でこちらを睨みつけている。
「お母さん、なに言ってるの……」
「私に子どもはいません!」
半ば叫ぶようにして、母ぱぴしゃりとそう言った。
「いたずら? 警察呼びますよ」
「ご、ごめんなさい……!」
わたしは思わずそう謝って、玄関から飛びだした。背中から、玄関の扉の閉まる重い音が聞こえた。
カナメさん……!
わたしはまた駅に向かいながら、携帯電話を取りだし、カナメさんに電話をかけた。
「もしもし?」
「わたしです、東雲アリカです……!」
「わ、わかってるよ? どうしたの、落ちついて……」
電話口から聞こえるカナメさんの優しい声に、わたしはいくらか落ちつきを取りもどす。
「あの、今晩、泊めてもらえませんか?」
「僕は構わないけど……」
「ありがとうございます。これから向かいます」
「うん、気をつけてね」
わたしはまた大学の最寄駅まで電車に揺られ、それから駅のすぐ近くにあるカナメさんの住むマンションへと向かった。カナメさんはマンションの外で佇んでいた。
「まさか、外で待っててくれたんですか?」
「まあ、夕涼み、だよ」
カナメさんはそう言って微笑む。夕涼みをするような気温ではなかったけれど、わたしはそれ以上なにも訊かなかった。カナメさんは、ゆっくりと階段を昇っていく。わたしはその後ろを着いていって、カナメさんが押さえてくれた扉をくぐった。
「でも、どうしたの、突然」
わたしは靴を脱いで揃え、狭いキッチンに足を踏みいれた。カナメさんはわたしの横を通りぬけてベッドに腰かけ、その隣を右手でぽんぽんと叩く。
「嫌じゃなかったら、ここに座って。話ならいくらでも聞くよ?」
招かれるままにカナメさんの隣へ腰かける。急に涙が溢れだした。
「アリカちゃん……?」
「母が……、母まで、わたしのこと……、忘れちゃったんです……。おかしいんです、みんな、わたしのこと忘れちゃった……。三谷先生も、川口さんも、林さんも、佐々木さんも……、ホツエも、シズエも……。母も……。そんなこと、ありえますか? ねえカナメさん、カナメさんは、わたしのこと、忘れたりしませんか? ずっと覚えててくれますか?」
泣きながらわけのわからないこと——自分でも、それがどれだけ「わけのわからないこと」なのかだけは、よくわかっていた——を、まくしたてるわたしの肩に、カナメさんはその左腕を優しく乗せた。そのままゆっくりと引きよせられる。それから右手で頭を撫でられた。
「忘れるわけないよ。だって……」
カナメさんはそこで一度言葉を区切って、ふっと息をついた。
「こんなに、好きなんだから」
わたしは泣きつづけながら、ひたすらカナメさんの胸に身を預けていた。
「おはよう」
肩を叩かれて、わたしは目を覚ました。いつの間にか、わたしはベッドに横たわっていた。
「泣きつかれたのか眠っちゃったから、そっとしといたよ。あ、僕は床で寝てたから、なにもしてないから安心して?」
「ありがとうございます……」
わたしは身を起こして、とりあえずベッドに腰かける。隣にカナメさんも座った。
「君が水曜日の一限に講義を取ってるかどうか、わからなかったから、起こしちゃったけど……。もし取ってるなら、そろそろ準備したほうがいいんじゃないかと思って」
「ああ……」
思わずうめいてしまう。カナメさんが心配そうにこちらを見た。
「三谷先生の講義なんですよね……」
「昨日、言ってたね。君のことを忘れてしまったって……」
「そうです。三谷先生、ものすごく記憶力がよくて……、一度見たものや聞いたものを絶対に忘れない、って言ってました。学生の顔も名前も、講義に何回きて何回遅刻したかも、全部覚えてて……」
「それはすごいなあ」
カナメさんが呟く。
「それなのに、それなのにわたしのこと、忘れちゃってたんです。絶対におかしいんです」
「うーん……」
困ったようにカナメさんは首を傾げる。
「三谷先生だけじゃないです。ホツエとシズエとは小学校からのつきあいなんですよ?それに、川口さんも林さんも佐々木さんも、ついこの間までわたしと普通に喋ってたのに……」
カナメさんはまた、うーん、と唸る。
「とりあえず、学校は休む?」
「はい……」
カナメさんに訊かれて、わたしは小さく頷いた。
「そっか。じゃあ僕もサボっちゃおうかな」
「えっ、いや、そんな……。わたしはカフェかどっかで時間つぶしますから……」
「いいんだよ。これまでけっこう真面目に講義受けてきたし、ちょっとくらいサボってもバチは当たらないよ」
どこか楽しそうにそう言うカナメさんにわたしは、はあ、と曖昧に頷く。
「朝ご飯作るよ。それとも、もう一回寝る?」
「えっと、朝ご飯、食べたいです」
「わかった。大したものじゃないから、期待はしないでね」
カナメさんはそう言って、キッチンに立った。
「たとえ世界が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから……」
まな板を置いて抽斗から包丁を取りだしながら、カナメさんが歌うように呟いた。
「僕の大好きな曲のサビ、こういう歌詞なんだ」
「『デクレッシェンド』ですか?」
「そうそう。よく覚えてたね」
カナメさんはこちらを見て、にっこり笑う。
わたしはまた泣きそうになるのをなんとか堪えて、机の上に視線を走らせた。
いつまでもカナメさんの部屋に居候しているわけにもいかない……。かと言って、実家にも帰れない。ひょっとしたら、大学の籍なんてとっくの昔に消えてなくなっているのかもしれない。いったいどうしたらいいのだろう。
なにも考えたくなかった。
24.
目が覚めて、あたりを見回した。部屋は真っ暗だ。まだ朝にはなっていないらしい。わたしはベッドに横たわっていて、床にはカナメさんがこちらを向いて眠っているようだった。わたしはなんだか心細くなって、カナメさんの体を揺すった。
「あれ……」
カナメさんは目を覚ましてわたしを見ると、びっくりしたような顔をした。
「すみません、どなたですか……? なんだか記憶が……。もしかして僕、あなたになにか……」
ああ……。頭が真っ白になり、それなのにわたしの口は勝手に動いた。
「いえ……、泥酔していたわたしを介抱してくださったんです。わたしにベッドを貸してくれて、自分は床で寝るから、って。ご迷惑をおかけしてすみません。ありがとうございました」
真っ白になった頭の中に、自分がついている嘘が流れこんでくる。カナメさんは不安そうな顔のまま、口を開いた。
「そうだったんですか……。僕も酔ってたんでしょうね、まったく記憶がなくて……」
「ええ、酔ってはいたみたいです。とにかく、なにもありませんでしたから」
「それなら、良かったんですが……」
カナメさんはそう言って体を起こし、部屋の電気をつけた。
「お邪魔してすみませんでした。わたし、帰りますね」
わたしは鞄を手に取って、玄関へ向かう。
「待ってください」
カナメさんの声に、思わず振りかえった。
「泣いているんですか……? やっぱり僕……」
「違うんです、昨日はいろいろあって……。親と喧嘩して実家を追いだされて、それで、ヤケ酒を飲んで……」
お酒なんて、飲んだことないのに。嘘を重ねれば重ねるほど、涙が重くなる。
「こっちに来ませんか。もう少し休んだほうがいいですよ」
一刻もはやくこの部屋から出ていかなければならない、そう思いながらも、わたしの足はふらふらと、カナメさんの傍まで歩く。
「なんだか、不思議なんです」
わたしは薄い青色のクッションの上に腰をおろした。カナメさんはベッドに腰かけて、わたしを見下ろしながら優しい声で呟く。わたしは、なにが不思議なんですか、と訊ねた。
「あなたのことは知らない、昨日のことも思いだせない、それなのに……、初めて会った気がしなくて。ずっと昔から知っているような、そんな気がして……」
「カナメさん……」
わたしは思わず、そう呟いていた。
「どうして僕の名前を……?」
「あ、えっと……、昨日、教えてくれたから……」
回らない頭でとっさに、また嘘をつく。
「そうでしたか。あなたのお名前も、訊いていいですか? 昨日聞いてるかもしれないけど、思いだせなくて」
「わたしの名前は……」
……思いだせない。
「どうかしましたか?」
カナメさんは首を傾げてこちらを見ている。この人が何度も呼んでくれたはずの名前が、思いだせない。
「えっと……、わたし、あんまり自分の名前が好きじゃなくて……。昨日も教えてないんです。だから、秘密です。ごめんなさい」
どうしてわたしは、カナメさんに向かって、こんなにいくつも嘘を重ねているのだろう。
「そうだったんですね」
カナメさんは寂しそうに微笑んで、大丈夫ですよ、と頷いてくれた。
「たとえ世界が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから……」
わたしはつい先日カナメさんが教えてくれた歌詞を、呟いた。カナメさんがびっくりしたようにわたしを見る。
「知ってますか、この歌詞」
「ええ、僕の好きな曲に、そんな歌詞があります。あなたもあの曲を、知っているんですか?」
「いえ……、ある人がその歌詞だけ、教えてくれたんです」
「たとえ世界が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから」
カナメさんは少し間を置いて、言葉を続ける。
「たとえ僕が君を忘れても、それでも僕はずっと君の傍にいるから……」
「えっ?」
わたしは思わず裏返った声をあげる。
「もしかして、前半しか教えてもらえませんでした? この歌詞、サビの部分なんですけど、最後のサビでは今のが続くんですよ」
——たとえ僕が君を忘れても、それでも僕はずっと君の傍にいるから。
「知らなかったです……。前半しか、教えてくれなかったなあ……」
カナメさんが、ふふ、と小さく笑った。
「その人にとって、きっとあなたは大切な存在なんでしょうね」
「どうしてですか?」
「だって……、大切な人に向かって『たとえ僕が君を忘れても』なんて、言いたくないじゃないですか。少なくとも、僕は、ちょっと言えないかなあ、って」
わたしは思わず俯いて、また溢れそうになる涙を堪えた。
「あ、ごめんなさい……。気を悪くしましたか?」
「いえ……、なんだか、その……、じーんとしちゃって……」
「そうだ、その人を頼ることはできないんですか?」
「そうですね……」
次はどんな嘘をつけばいいのだろうか、と頭を働かせながら、わたしは答える。結局、まともな嘘は思いつかなかった。カナメさんは少し不安そうに首を傾げる。
「あの、大丈夫ですか?」
「はい……。すみません、コーヒーもらえませんか?」
「いいですよ、淹れましょうか」
カナメさんは立ちあがって、キッチンに立った。
25.
「カナメさん……」
床で眠っているカナメさんの顔を見つめながら、その名前を呼んでみる。自分の名前は思いだせないのに、カナメさんの名前はちゃんと覚えている。
わたしは突然、携帯電話の存在を思いだした。ポケットから携帯電話を取りだすと、画面に数字のボタンが表示される。パスコド……。パスコード、なんだっけ。誕生日? 誕生日って、いつだっけ……。
わたしは携帯電話を諦めて、机の上に伏せて置いた。カナメさんが起きあがったので、びっくりして思わずのけぞった。
「起こしちゃいましたか……?」
おそるおそる問いかけてみたが、カナメさんは答えてくれなかった。首をひねって壁にかかった時計に目をやっている。そして、小さく溜息をつく。
「カナメさん?」
さっきより少し大きな声で呼びかけてみたが、返事はない。胸がざわつく。カナメさんは立ちあがり、キッチンでコーヒーを淹れはじめた。手元にマグカップを一つだけ用意して。
「あの……、わたしも、飲みたいです……」
おずおずとそう声をかけるものの、カナメさんはこちらを振りかえりもしなかった。コーヒーを淹れおわると、カナメさんはマグカップを手に、ベッドの真ん中に腰かけた。コーヒーを一口すすってマグカップを机の上に置き、リモコンを手にとってテレビの電源を点ける。わたしはいったいどうすればいいのかわからず、薄い青色のクッションの上に座った。
カナメさんはぼんやりとテレビの方に顔を向けている。わたしは、なにかカナメさんの気に障ることをしてしまったのだろうか。それでカナメさんは怒って、わたしを無視しているのだろうか。いや……。カナメさんは腹が立ったからといって相手を無視するような人じゃない。でも、それならどうして?
チャイムが鳴った。カナメさんはテレビを消してベッドから立ちあがり、玄関へ向かう。カナメさんが開けた扉の向こうには、林さんが立っていた。
「林さん……!」
せめて「あんた誰?」と言ってほしい。そう願いながらわたしが名前を呼んでも、林さんはこちらに目をくれることさえなく、カナメさんと一緒に部屋に入ってきた。カナメさんは再びベッドに腰かけ、そんなカナメさんを見下ろすようにして林さんが立つ。
「どうしたの、ユウ?」
「どうしたのって……。ずっとサークル来てないだろ。電話も繋がらないし、まあその……、心配で見にきた」
「ああ、ごめん……。そういえば携帯電話、サイレントモードのままにしてたかも……。サークルに行ってないわけじゃなくて……、いやまあ、行ってないんだけど……、そもそも学校に行ってないんだ」
「なんでだ?」
林さんの問いかけに、カナメさんは黙りこむ。
「いつまで休むつもりなんだ?」
「さあ……」
「なにかあったのか。その……、俺でよければ、話ぐらい聞くけど」
林さんはどこかぶっきらぼうにそう言った。カナメさんは黙っている。
「そうか、言いたくないならべつに……」
「いや」
言いかけた林さんを、意を決したかのようにカナメさんが遮る。
「なんだか、すごく大切なことを、僕は忘れてしまった気がするんだ」
「大切なこと?」
「どうしても思いだせない。でも、どうしても思いださなくちゃいけないんだ」
林さんは困ったように、小さく溜息をついた。
「わかってるよ、わかってるけど……、それ以外にどう言えばいいのか、わからないだ……」
「こんな狭い部屋の中に一人でいるから、思いだせないんじゃないか?」
——こんな狭い部屋の中に一人でいるから。
わたしは林さんの言ったその言葉を、二度三度と頭の中で繰りかえした。わたしは、この部屋に、いない……。カナメさんも林さんも、わたしを無視しているわけじゃない……。
「いや……、ここで、この部屋で、思いださなくちゃいけないんだ」
「はあ……?」
「とにかく僕は、それを思いだすまで、この部屋から出ない」
カナメさんがきっぱりと言いはなつ。
「勝手にしろ……」
林さんは呆れたように、カナメさんに背を向けた。
「ただ、もし俺にできることがあれば……、そんなものがあるのかは知らんが、とにかくそのときは電話でもしてくれ」
林さんは玄関に向かい、靴を履いて立ちあがり、そこで止まった。なにかまだ言うつもりなのだろうか、と思ったが、結局林さんはなにも言わずに玄関の扉を開けて、そのまま外へ出ていった。
カナメさんが長く息をついた。そして、壁の隅に立てかけてあるギターを手にとり、ベッドに腰かける。机の上の缶を開けてカポタストを取りだし、ギターに嵌める。カナメさんが奏ではじめたのは、いつかこの部屋に来たときに、わたしに聴かせてくれた曲だった。
「空はどこから空なのだろう」
カナメさんが、曲にあわせて綺麗な声で、そっとそっと歌う。
「この手を伸ばせばもう、届いているのかもしれない。あの星はまだあるのだろうか。光だってゆっくり歩いてくる」
まるで自分自身に聴かせるように、あるいは誰にも聴かせたくないかのように。
「泣きたくないのに涙が出ちゃう。君は笑うのが上手じゃないね。けれどそんな君が好きでたまらないよ」
それともひょっとしたら、誰かに聴いてもらいたいかのように。
「いつだって夢を見ている。叶わなくても構わないんだ。君の愛した花が枯れてしまう。そうだとしても水をやろうか」
わたしはただただカナメさんの歌声に耳を傾ける。なるべく息を止めて、一言も一音も聴きのがすまいと。
「もう夜だけど眠りたくない。おはようって言わせてくれないか。そんなに寂しそうな顔をしないで」
カナメさんは目を閉じて、息継ぎをした。
「たとえ世界が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから」
カナメさんは両手を動かしつづけた。弦を押さえる左手と、弾く右手。
「空はどこまで空なのだろう。いつかはその向こうへ、届くことができるだろうか。あの星はもうないのだろうか。光だって疲れて止まるだろう」
六本の弦とカナメさんの声が奏でるその音楽を、わたしはずっと聴いていたいと思った。
「泣きたいときには涙が出ない。君は生きるのが上手じゃないね。だからそんな君が好きでたまらないよ」
涙が出そうになって、自分の目尻に手をあてた、いや……、あてようとした。
「今日だって現抜かすよ。怒られたって仕方ないんだ。僕の嫌いな花がまだ咲いている。いつまでだって実を結べない」
わたしは、自分がもはやそこに存在しないことを、どうしても受けとめなければならなかった。改めて自分の手を見ようとしたが、うまくいかなかった。もう、わたしの手など、なかったから。
「まだ朝だけど起きたくないよ。おやすみって言わせてくれないか。そんなふうに優しい顔をしないで」
カナメさんはまたぎゅっと目を閉じて、大きく息継ぎをする。
「たとえ世界が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから。たとえ僕が君を忘れても、僕はずっと君の傍にいるから」
ギターの音がゆっくりと小さくなっていき、そして消えた。カナメさんはギターの上にくずおれ、やがて小さな嗚咽を漏らしはじめた。わたしはそっと、カナメさんの横に腰かけた——いや、腰かけることは、できなかった。手だけでなく、足も、胴体も、もうなかった。カナメさん。そう呼びかけようとしても、声は出てこなかった。
——さようなら。
カナメさんにも、自分の耳にさえも、届かない言葉を必死で絞りだす。それは音にならなかった。
それでも、カナメさんがはっと顔をあげるのが、わかった。